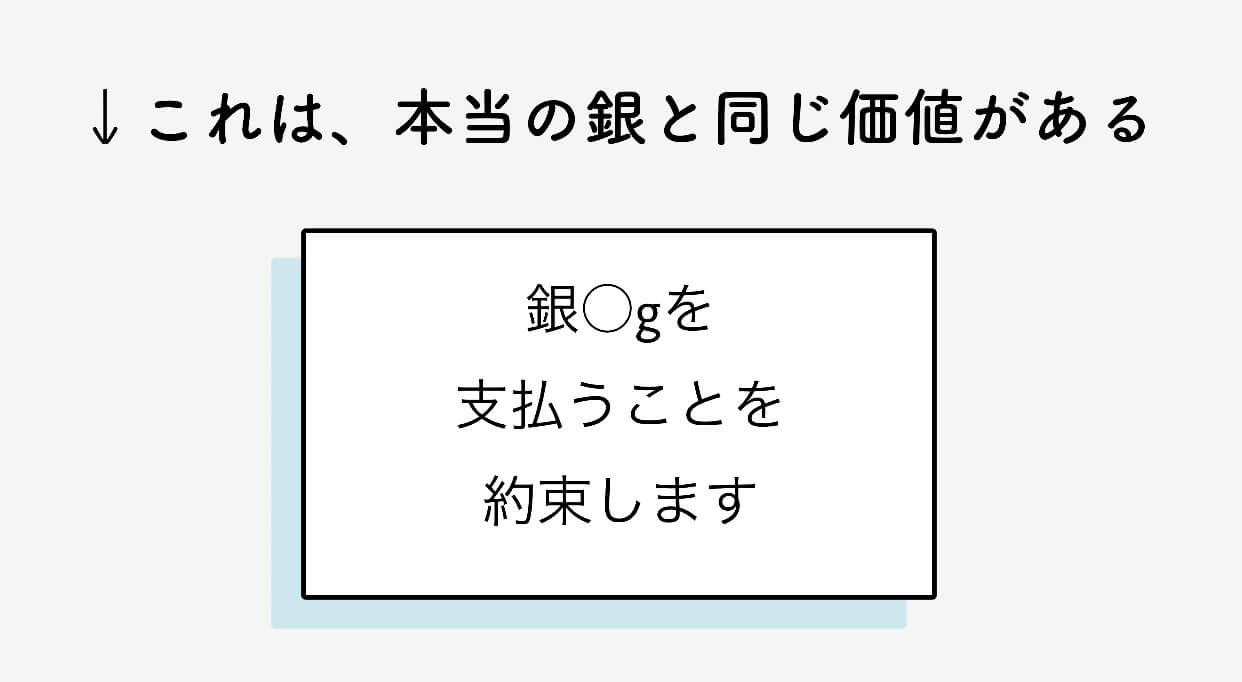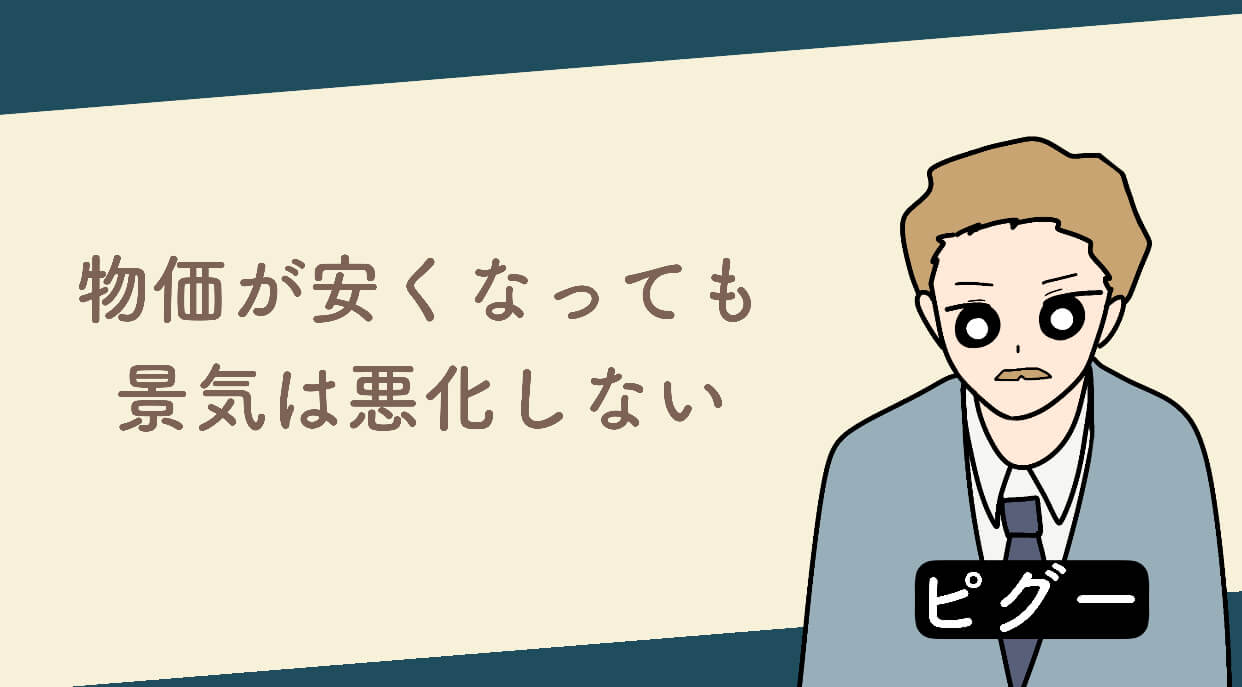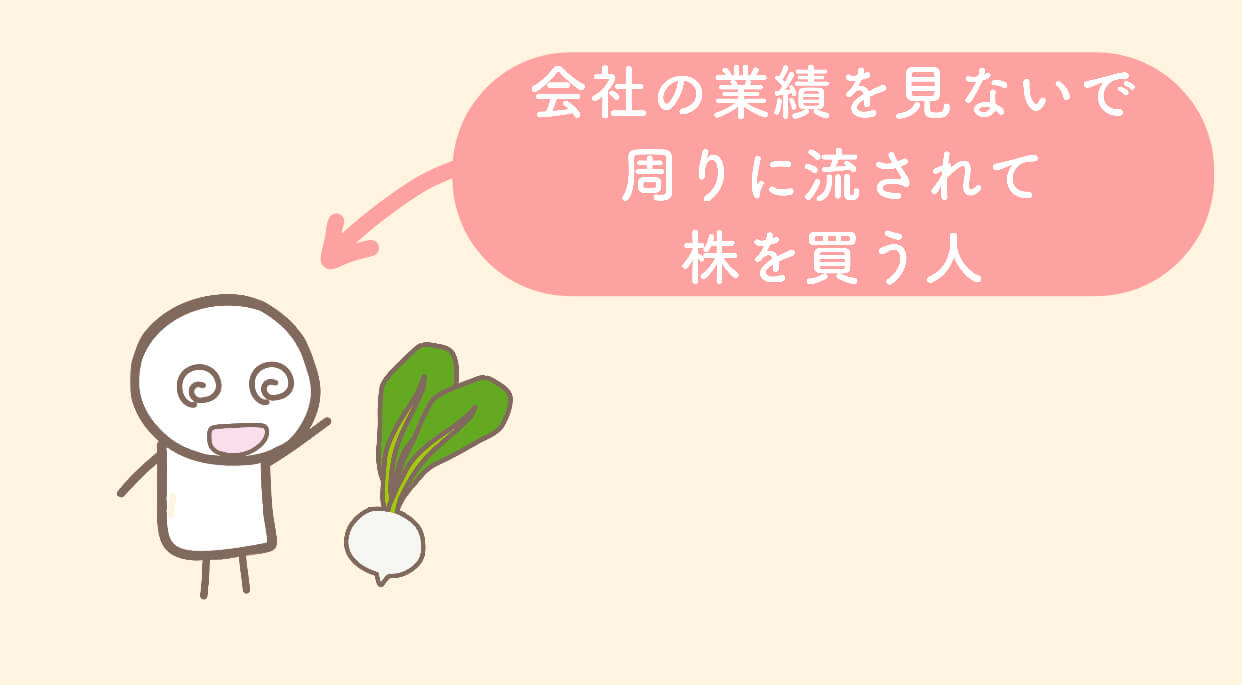本位
本位とは「何かを中心とする」という意味です。
例えば「自分本位」は、自己中という意味です。
商品本位制
商品本位制とは、商品がお金として使われる制度のことです。
例えば、金や銀、タバコ、スズのような品物がお金として使われていた歴史があります。
本位制とは「それを基準にする」「それをお金として使う」という意味です。
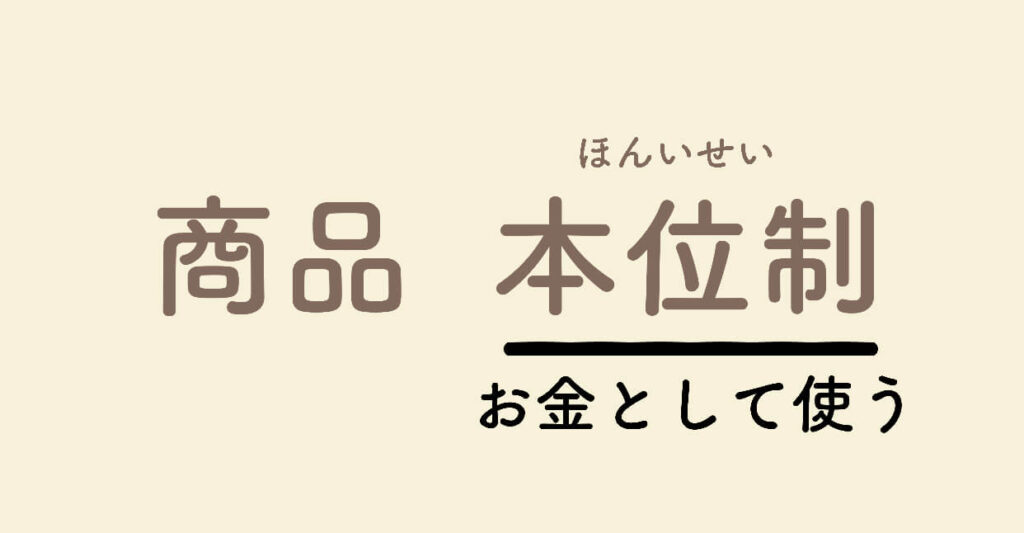
また、金(キン)をお金として使うことを「金(キン)本位制」と言います。
金や銀のような資源には限りがあるので、大量生産ができません。
大量生産ができないことは、メリットにもデメリットにもなります。
メリット
メリットは、インフレにならないことです。
インフレとは、世の中にお金が増えすぎて、お金の価値が下がってしまうことです。
金や銀などの資源は、大量生産ができないため、インフレになる心配は必要ありません。
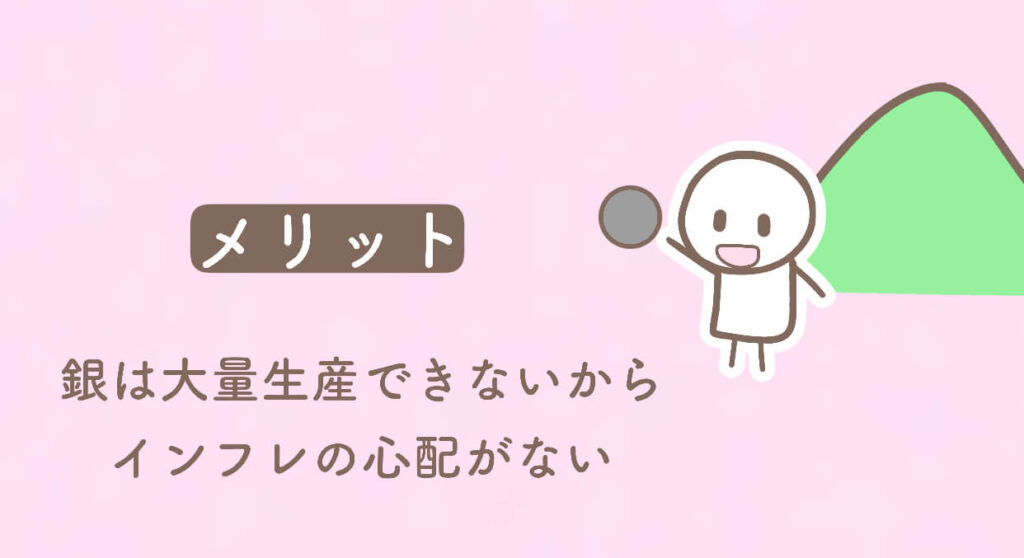
インフレの心配はないので、政府がお金の量を管理(増やしたり、減らしたり)する必要はなくなります。
デメリット
デメリットは、通貨供給量を増やすには、資源が必要だということです。
お金を増やしたい時は、南アフリカの地中に眠っている銀を掘り出して運ばないといけません。
それは、とても大変です。
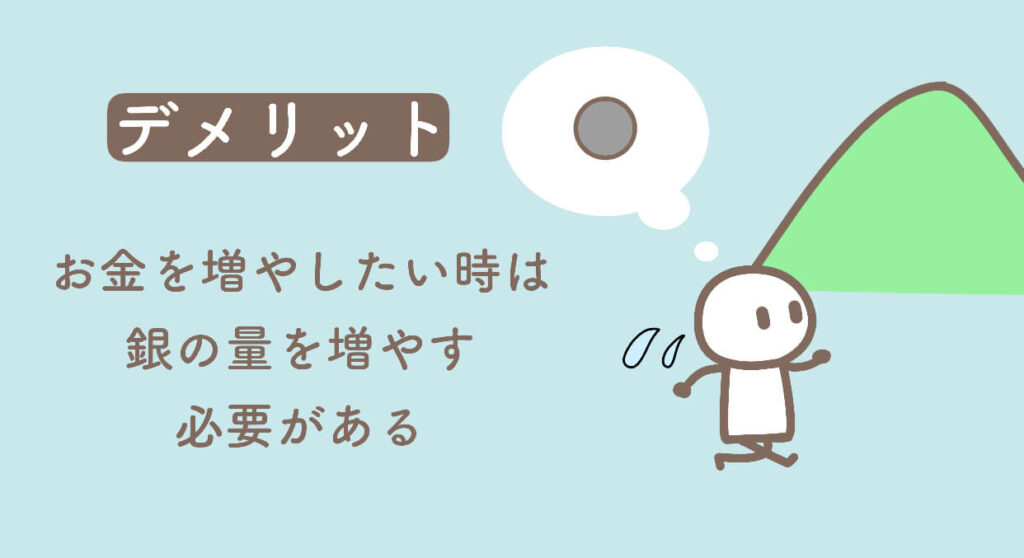
紙のお金の方が簡単にたくさん刷ることができます。
紙幣が生まれた背景
紙幣とは紙のお金のことです。
紙幣が生まれた理由の一つは、銀を掘り出して、運ぶのは大変だからです。
資源がなくてもお金を作る方法を探した結果、紙幣のお金が生まれました。
たとえば「銀○gを支払うことを約束します」と印刷した紙切れを作れば、この紙切れは本当の銀と同じ役割を果たすことになります。

このように、紙の発行量を銀の量と同じようにすることを「銀本位制」と言います。
商品本位制の崩壊
しかし、保有している金や銀の量よりも、もっと多くのお金がある方が便利だ、という意見も出てきます。
そして、中央銀行が国のお金を増やしたり減らしたり、コントロールするべきだ、という意見も増えていきます。
お金は簡単に刷れるので、苦労しないで、国のお金を増やすことができます。
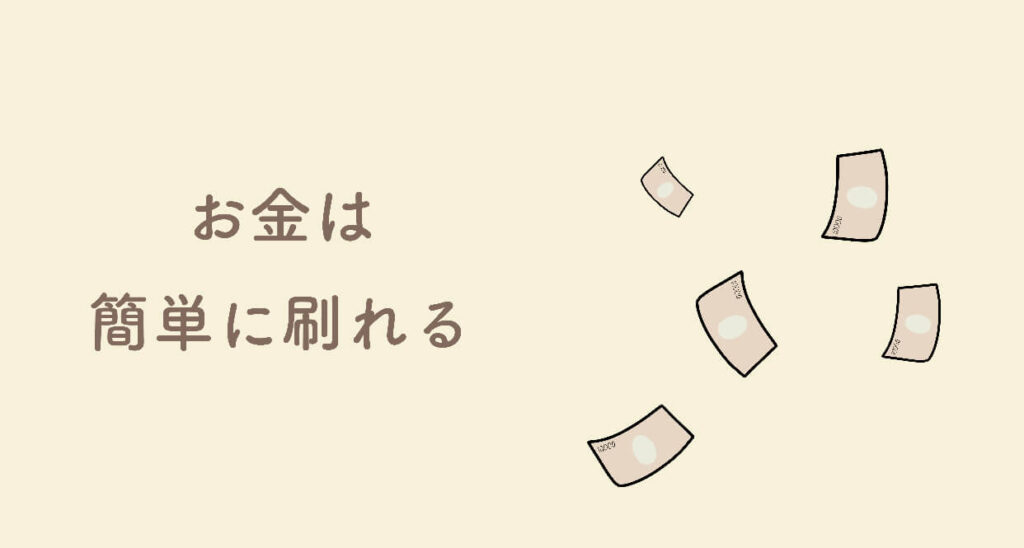
しかし、これが欠点になってしまうとフリードマンは考えました。
中央銀行は、お金の量をいい感じにコントロールできるほど、天才ではないのです。
たとえば、1930年代、本来ならお金を増やすべきタイミングで、間違ってお金の量を絞ってしまったことがありました。
このような裁量的なやり方は、景気を悪化させる原因になると、フリードマンは主張しています。
もともと中央銀行は、「金と紙幣を交換できることを保証する」だけの場所でした。
それが、どんどん力をもって、いまでは景気のコントロールという大きな責任を負うようになりました。
中央銀行が強力な裁量権を持つようになって、人々の生殺与奪権を握り始めてしまったことに、フリードマンは焦りを感じています。