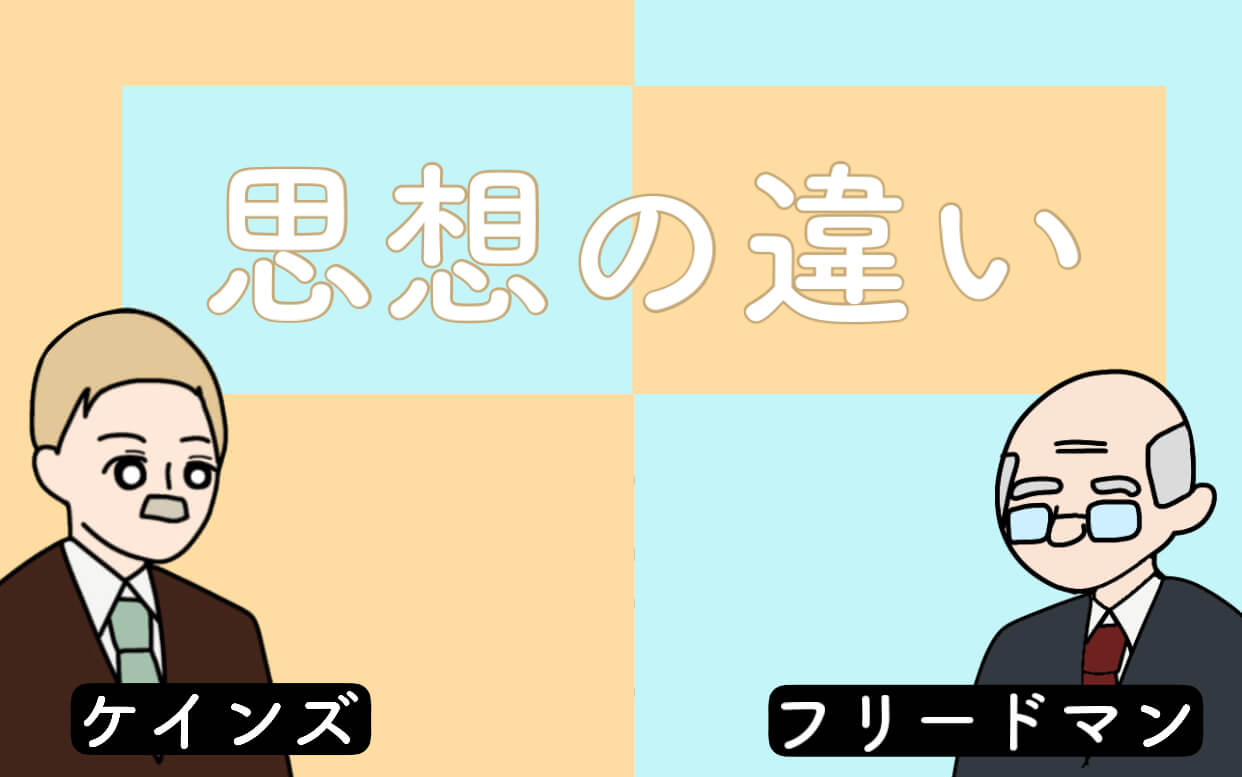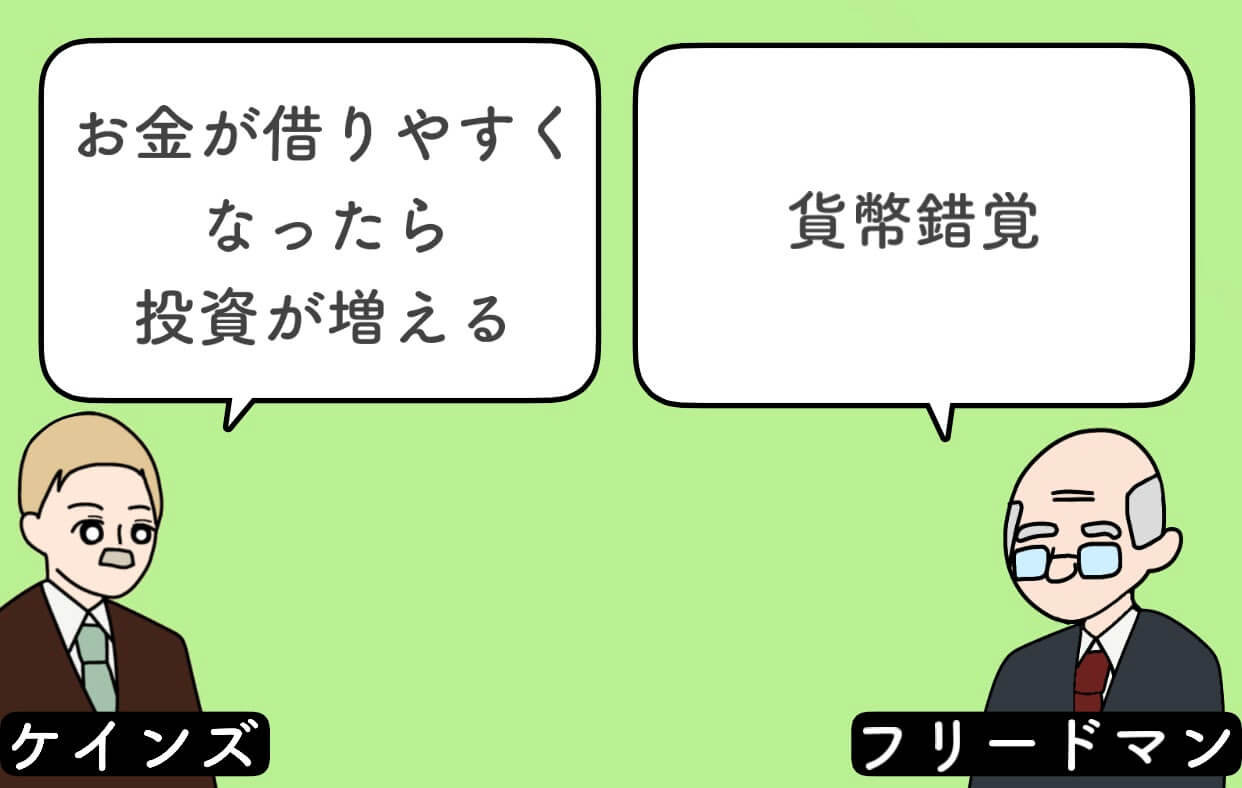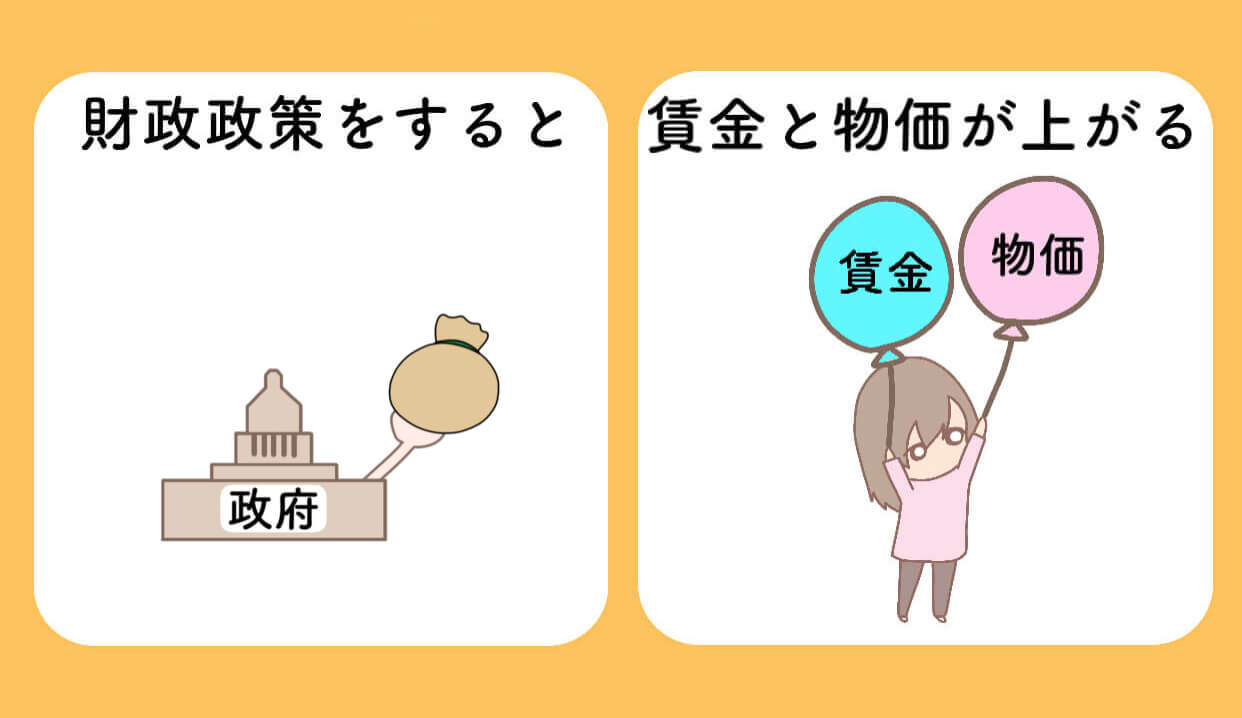ケインズとフリードマンは、意見が対立した経済学者です。
どのような意見の違いがあったのでしょうか?
ケインズ
まず、ケインズは、イギリス出身の経済学者です。
彼が生きた時代は、1930年代の「世界恐慌」という不景気の時代です。
そのころは、4人に1人が仕事を失うほど、貧困が広がっていました。
そのため、ケインズは「まずは、失業者を救済しよう」と考えました。
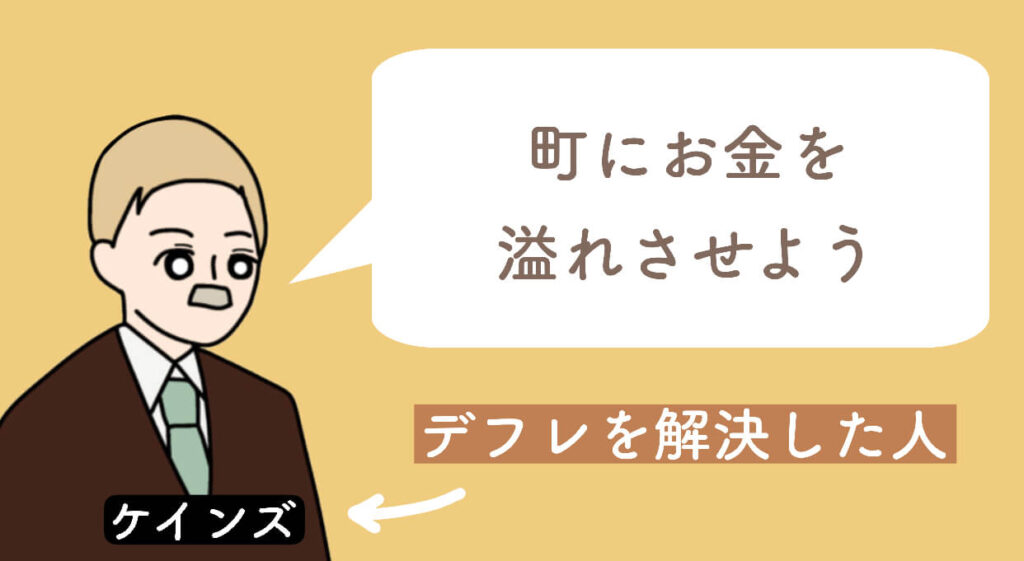
ケインズ経済学は、デフレ解決に有効だと言われています。
フリードマン
一方で、フリードマンはアメリカの学者で、ケインズの後の時代の人です。
彼の時代は「インフレ(物の値段がどんどん上がって困ること)」が大きな問題でした。
フリードマンは、インフレを解決する方法について、考えました。
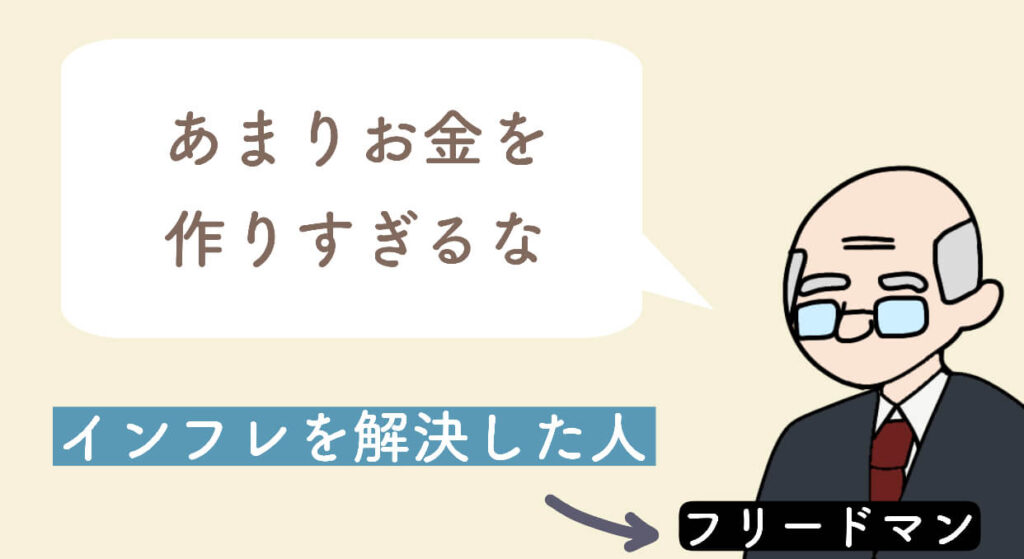
フリードマンは、インフレを解決することを大事にした考え方をしています。
考え方の違い
このように、ケインズとフリードマンは、生きていた時代が違うので、考え方に違いがあります。
ケインズは、景気が悪いときは、
- 国がもっとお金を使う(公共事業を増やす)
- 中央銀行が金利を下げて、お金を借りやすくする
といったやり方で、みんなにお金を回し、買い物や投資を活発にしようと考えました。
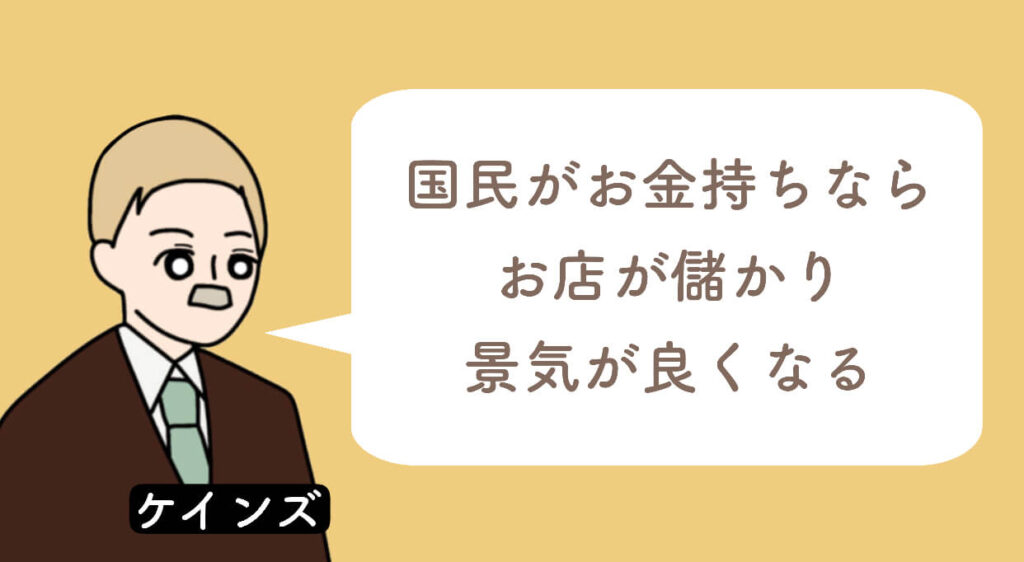
一方で、フリードマンは、ケインズのやりかたを批判しました。
フリードマンは、政府が当てずっぽうにお金を使うことに反対でした。
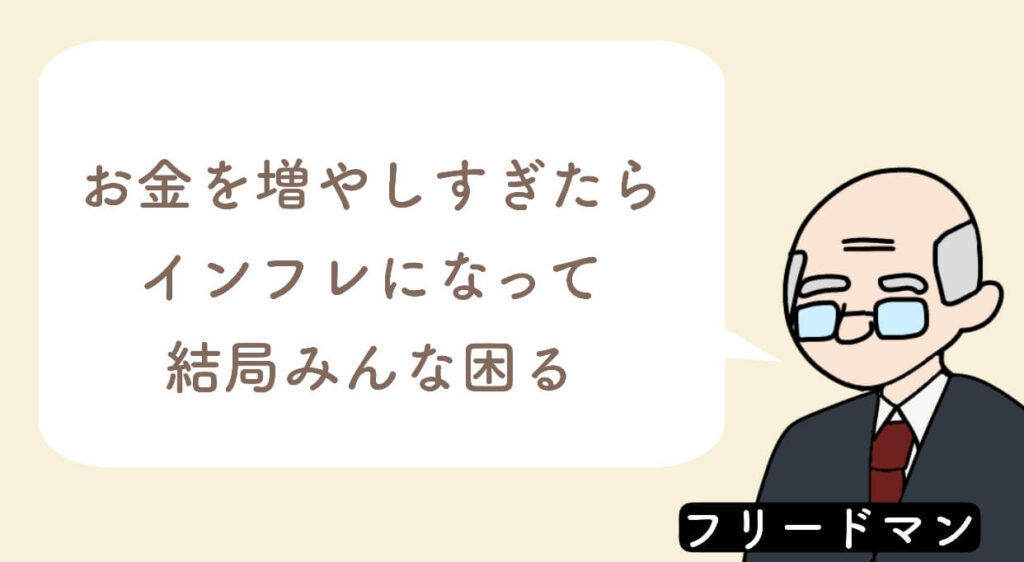
彼は「毎年、決まった量だけ、ルール通りにお金を増やすのが大事」と考えました(これを“K%ルール”といいます)。
それぞれの意見について、具体的に見ていきます。
金融政策
金融政策とは、中央銀行が「世の中のお金の量」を調整することです。
たとえるなら、「蛇口から水を出すように」お金の量をコントロールする感じです。
中央銀行は、水道の蛇口みたいです。
お金をじゃぶじゃぶ出すこともできます。
しかし、どれくらいお金を刷るのかの加減は難しいです。
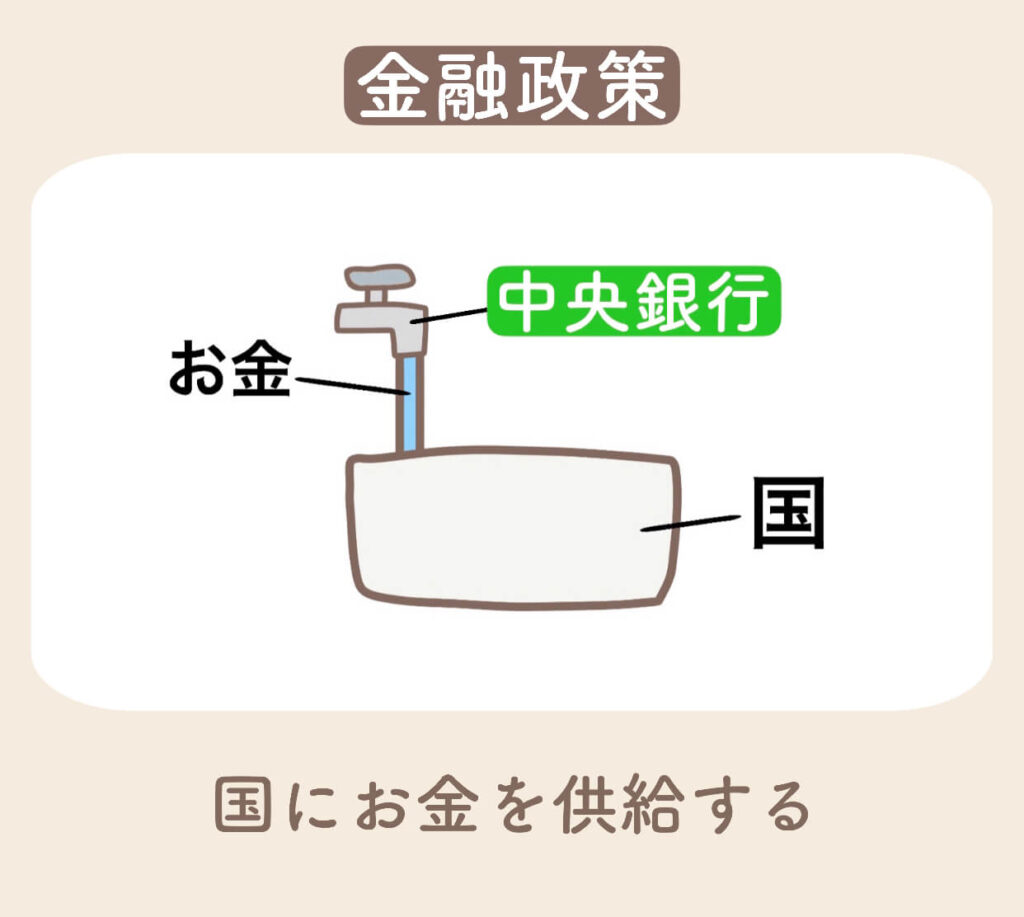
ケインズ
まずは、ケインズの意見です。
ケインズは、景気が悪い時は、国のお金をじゃぶじゃぶ増やすと、景気が良くなると考えています。
景気が悪い時は、お金をジャブジャブ出せば、町にお金が溢れます。
そして、国民がいっせいにみんなお金持ちになれば、買い物をする人が増えます。
買い物をするお客さんが増えれば、お店が儲かり、景気が良くなります。
「こうすることで、仕事が生まれ、景気がよくなる」と、ケインズは考えました。
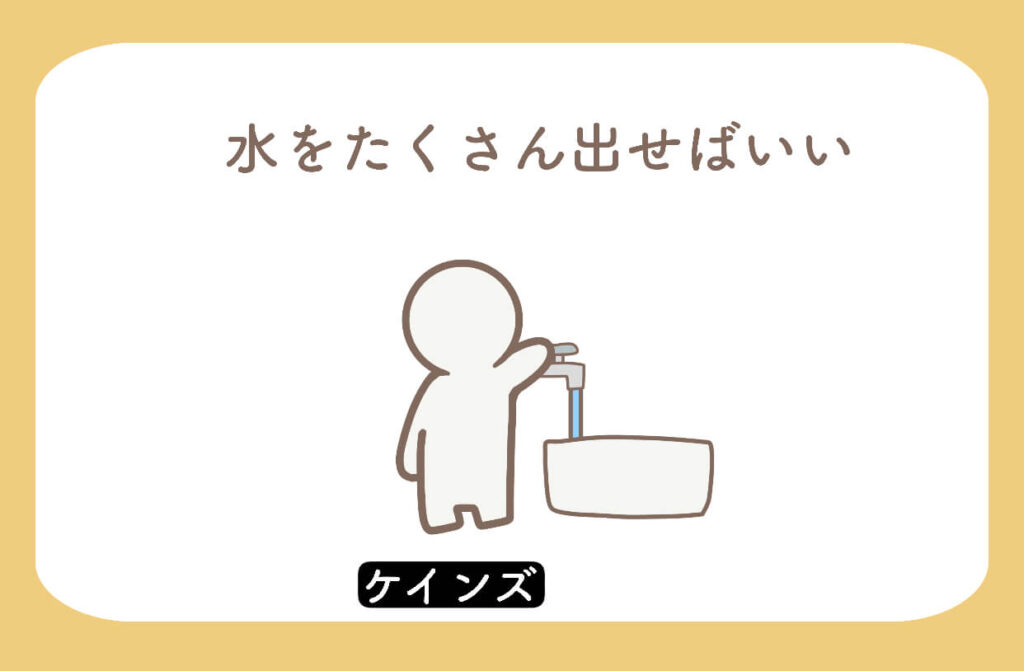
さらに、お店が儲かれば、お店が忙しくなって、新しく人を雇います。
つまり、働き口が増えます。
こうして、失業者を減らすことができるのです。
また、パンがよく売れる時は、パン屋さんはお店を大きくしようと考えます。
つまり、設備投資が増えます。
このように、ケインズは、世の中のお金が増えることで、景気が良くなると考えました。
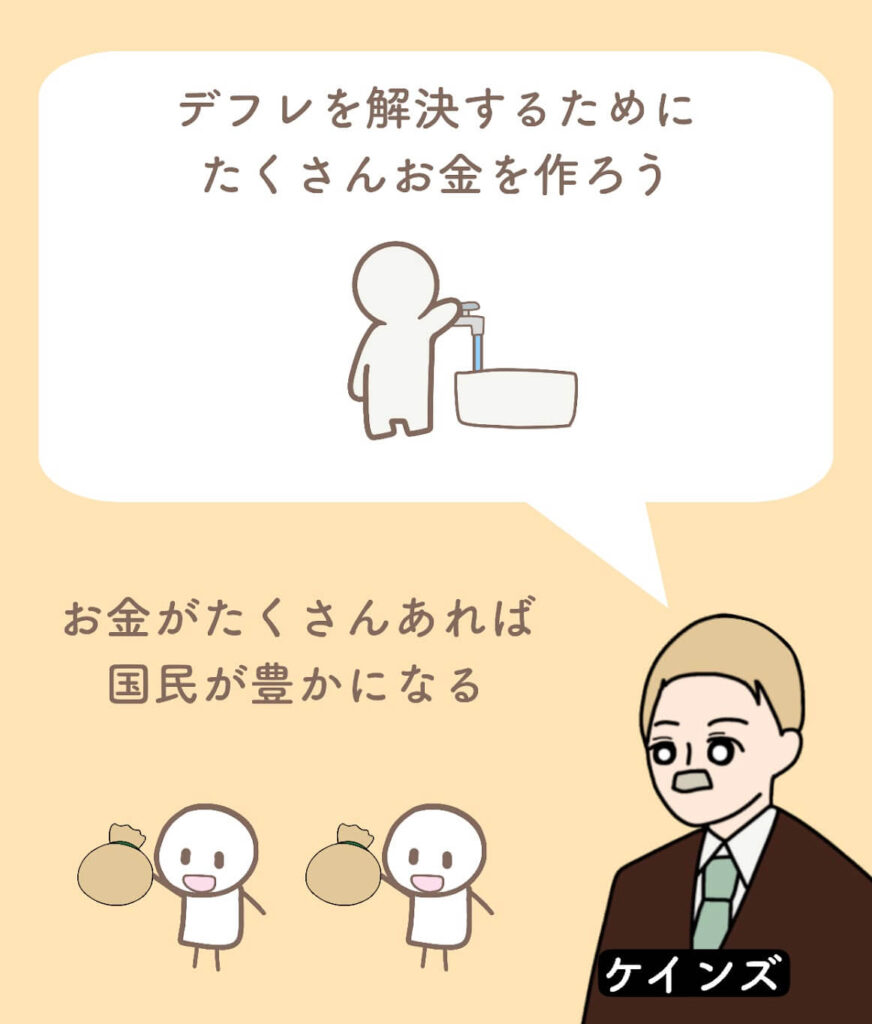
ケインズは「ガンガンお金を刷ろう」という考え方をしています。
なぜなら、お金が増えて、国民がお金をもらったら、国民が豊かになるからです。
「お金をたくさん刷って、デフレを解決するべきだ」とケインズは考えています。
フリードマン
フリードマンは、ケインズのやり方は、裁量的すぎてダメだと言います。
フリードマンのいう「裁量的」とは、「当てずっぽう」というニュアンスです。
状況に合わせながら、その場その場で考えて、臨機応変に対応することです。
しかし、そんなやり方では、水を出しすぎてしまう危険性もあります。
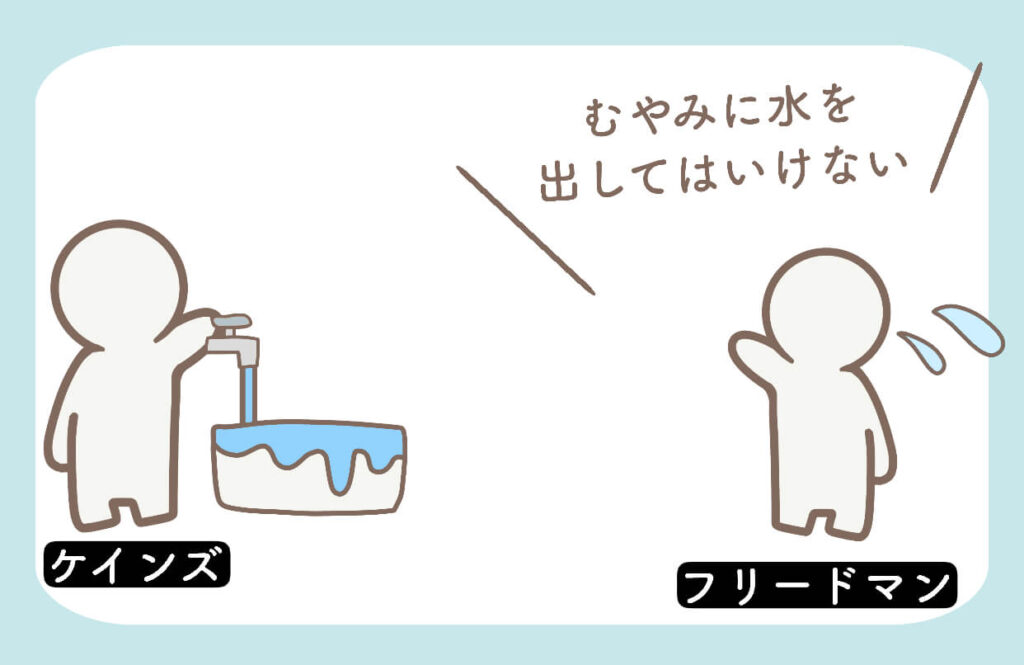
フリードマンは、裁量的な金融政策に反対です。
- お金を出しすぎると、物の値段が上がりすぎる(インフレ)
- だから、一定のルールにそって、少しずつお金を増やすのがよい
フリードマンは、金融政策は、当てずっぽうにやってはいけない、と考えました。
モノの量が増えていないのに、お金だけ増えてしまうと、インフレになってしまうからです。
インフレとは、お店の商品の値段がどんどん高くなることです。
国民がお金持ちになっても、お店のパンの値段が上がれば、買い物できる量は変わりません。
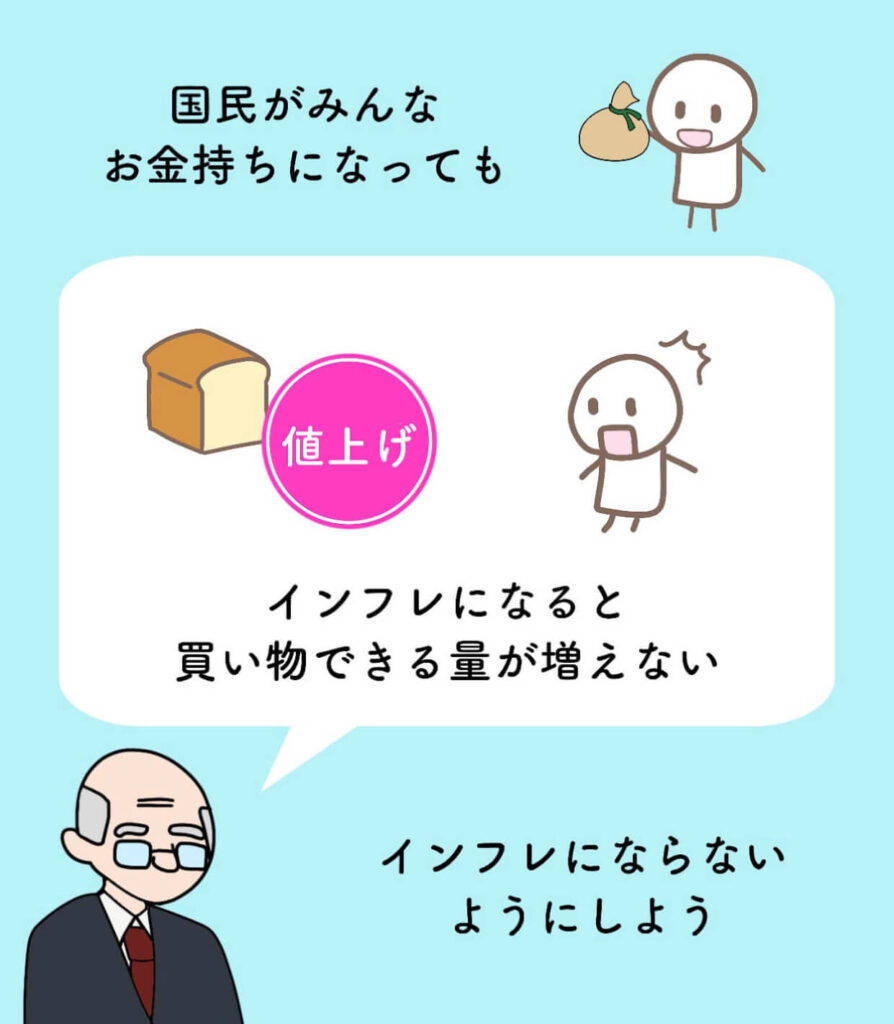
世の中のお金を増やすと、確かにお店の商品の値段が高くなります。
しかし、商品が高くなったら、お客さんが減ってしまいます。
お客さんが減ってしまえば、お店側は「もっと商品を作ろう」と考えません。
そのため、人を雇うこともありません。
このような考え方をしているため、フリードマンは、物価が上がっても、失業者は減らないと考えました。
そのため、フリードマンは、国の経済成長に合わせて、ルールに基づいて、一定の割合でお金を増やすべきだと考えました。
これを、K%ルールといいます。
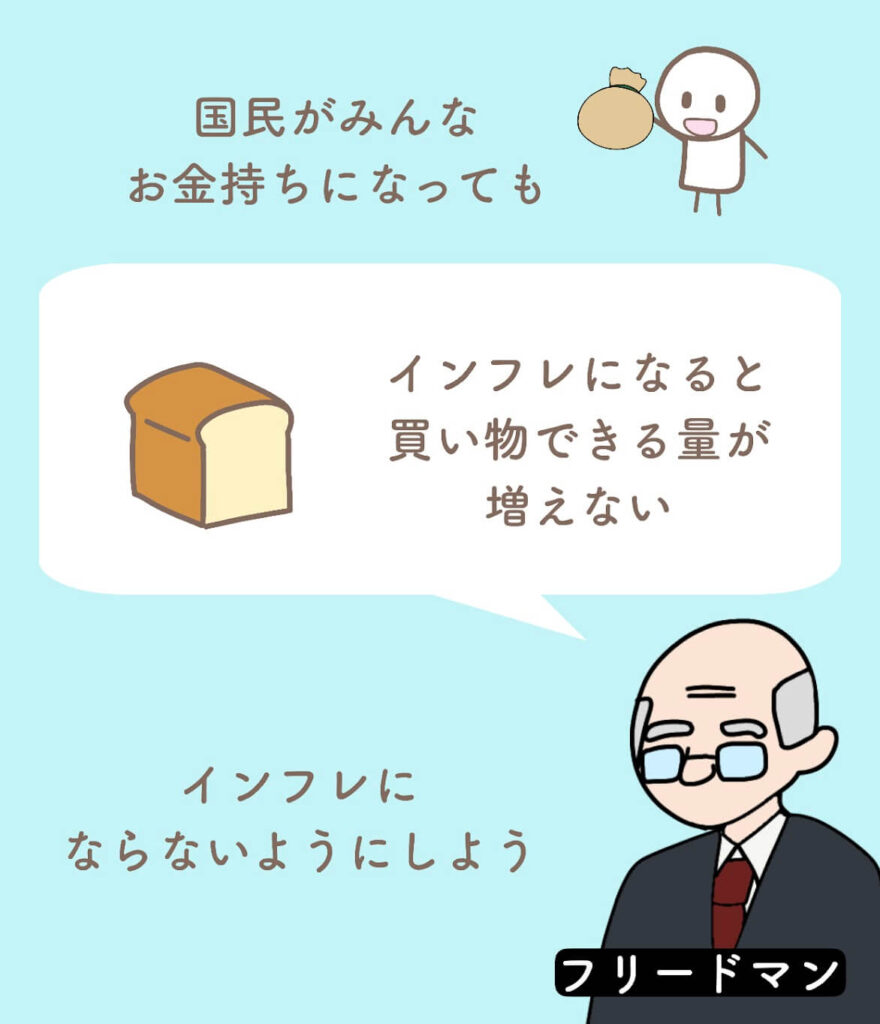
フリードマンはインフレを恐れて生きています。
たくさんお金を刷りすぎては、インフレになってしまいます。
ケインズの時代は、人々はデフレに困っていましたが、フリードマンの時代は、人々はインフレに困っていました。
そのため、どんどんお金を刷るのは、インフレになるから良くない、とフリードマンは言いました。
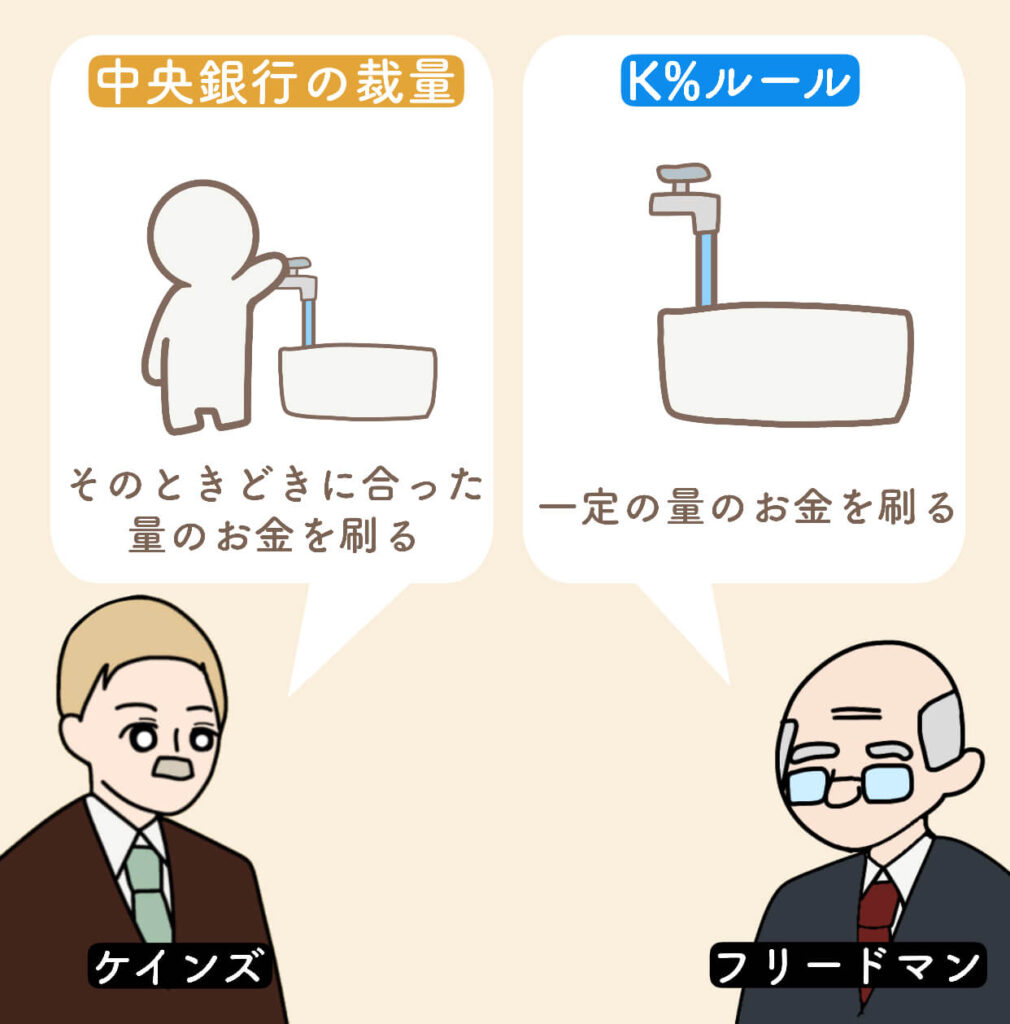
ケインズは「中央銀行で働いてる人にお任せして、臨機応変にお金を刷ってもらおう」と考えていました。
しかし、フリードマンは「中央銀行にお任せ」は良くないと考えました。
人は正しい判断ができない時が多いからです。
そのため、あらかじめルールを決めて、ルール通りに一定の量だけ、お金をするべきだと主張しました。
これをフリードマンはK%ルールと呼びました。
財政政策
ケインズは、財政政策に賛成しています。
一方で、フリードマンは財政政策に反対しています。
ケインズ
まず、ケインズの考え方からです。
財政政策とは、道路を作ったり、学校を建てたりする「公共事業」と「減税・増税」のことです。
- 国が公共事業をして、仕事を作れば、失業が減る
- 税金を下げて、みんなが買い物しやすくすれば、景気がよくなる
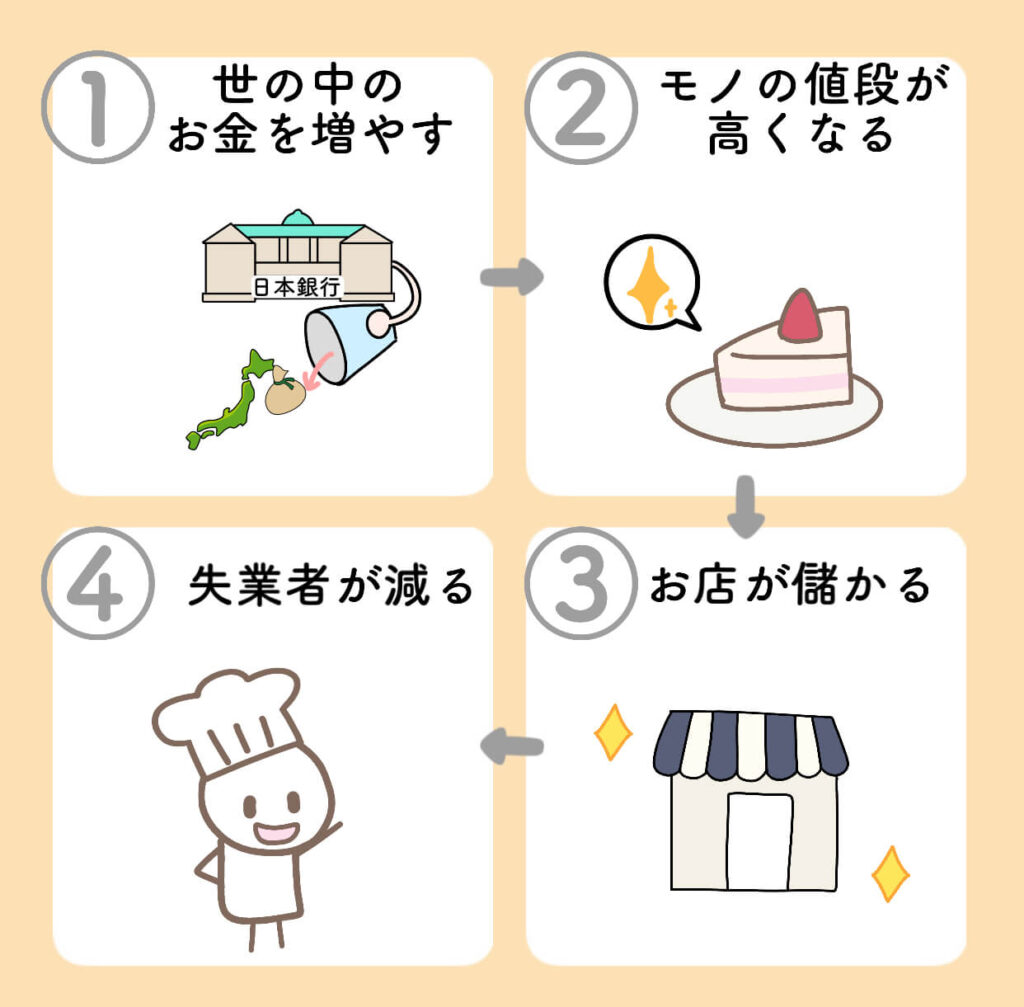
公共事業をするということは、働き口を増やすということです。
働き口が増えれば、失業者は働きやすくなります。
そして、失業者が労働者になることで、彼らの所得が増えます。
労働者は、給料をもらったら買い物をします。
こうして景気が良くなるのです。
ケインズは、財政政策をすることで、国民の所得が増えたら、失業率が減る、と考えています。
フリードマン
一方で、フリードマンは、財政政策に反対しています。
国民の所得が増えて、国民が買い物をするようになると、モノが高くても売れるようになります。
そして、物価が上がります。お店のモノの値段が高くなります。
どんどん値上がりすることは、お客さんにとっては、悲しいです。
そのため、買い物する人は減ります。
だから、財政政策で景気をよくすることはできない、とフリードマンは考えます。
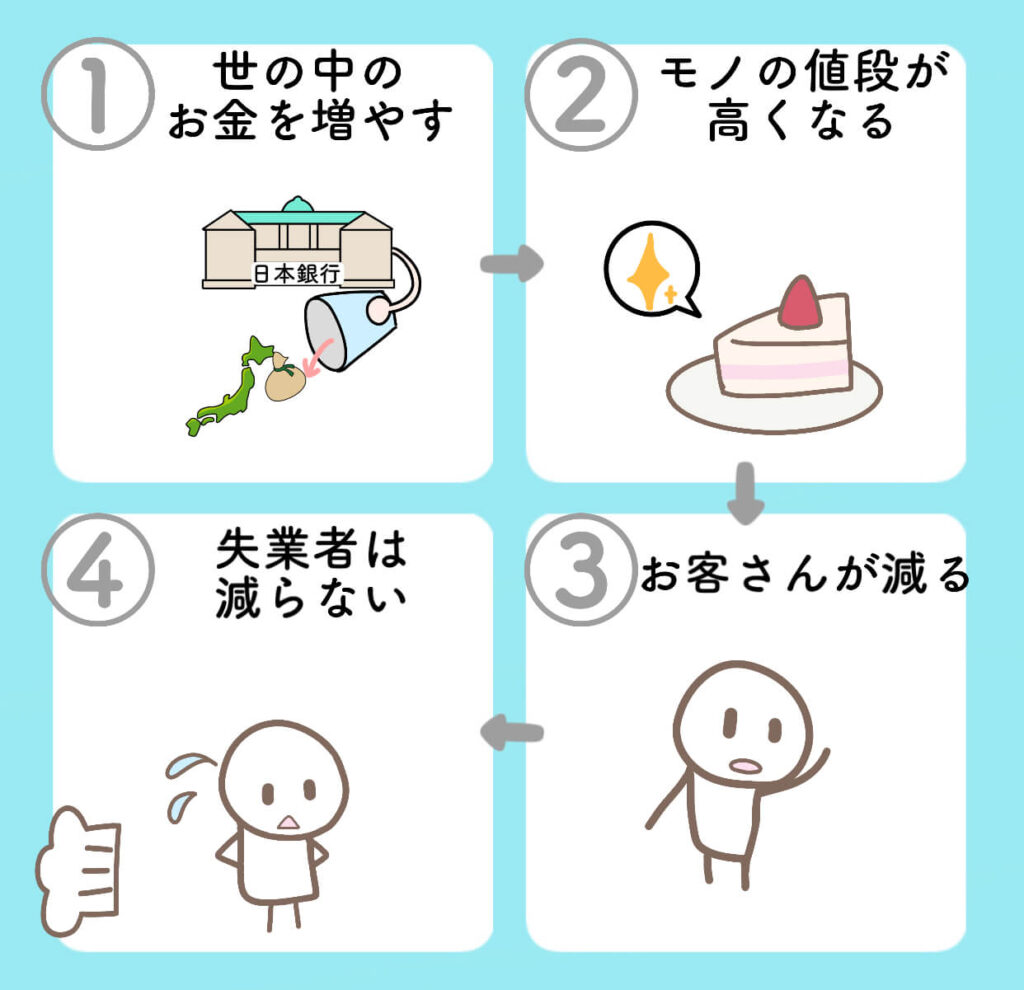
- 所得が増えると、物の値段も上がるので、買い物はあまり増えない
- だから、公共事業や減税は、あまり意味がない!
財政政策のメリットは、失業率が下がることです。
しかし、デメリットは、インフレになることです。
お店のモノの値段が高くなると、買い物する人が減るから、お店は儲からない、とフリードマンは考えました。
インフレとデフレの考え方
ケインズとフリードマンは、インフレ・デフレが起きる理由についても考え方が違います。
ケインズ
ケインズは、インフレ・デフレは、国にどれくらい失業者がいるのかで決まると考えています。
- 働いて給料をもらうと、買い物がたくさんできる
- だから、インフレになる
インフレの時は、商品が高く売れるということです。
商品が高く売れるなら、会社が儲かります。
そして、従業員にたくさん給料を払えます。
そして、商品が高く売れるうちに、もっと商品をたくさん売ろうと考えて、新しい従業員を雇います。
つまり、インフレになると、働き口が増えるのです。

逆に、デフレの時は、商品を安くしないと売れない状態になっています。
商品を安くしないと売れない時は、お店が儲かりません。
つまり、従業員に賃金が払えなくなり、クビにしないといけなくなるのです。
こうして、クビになる人が現れます。
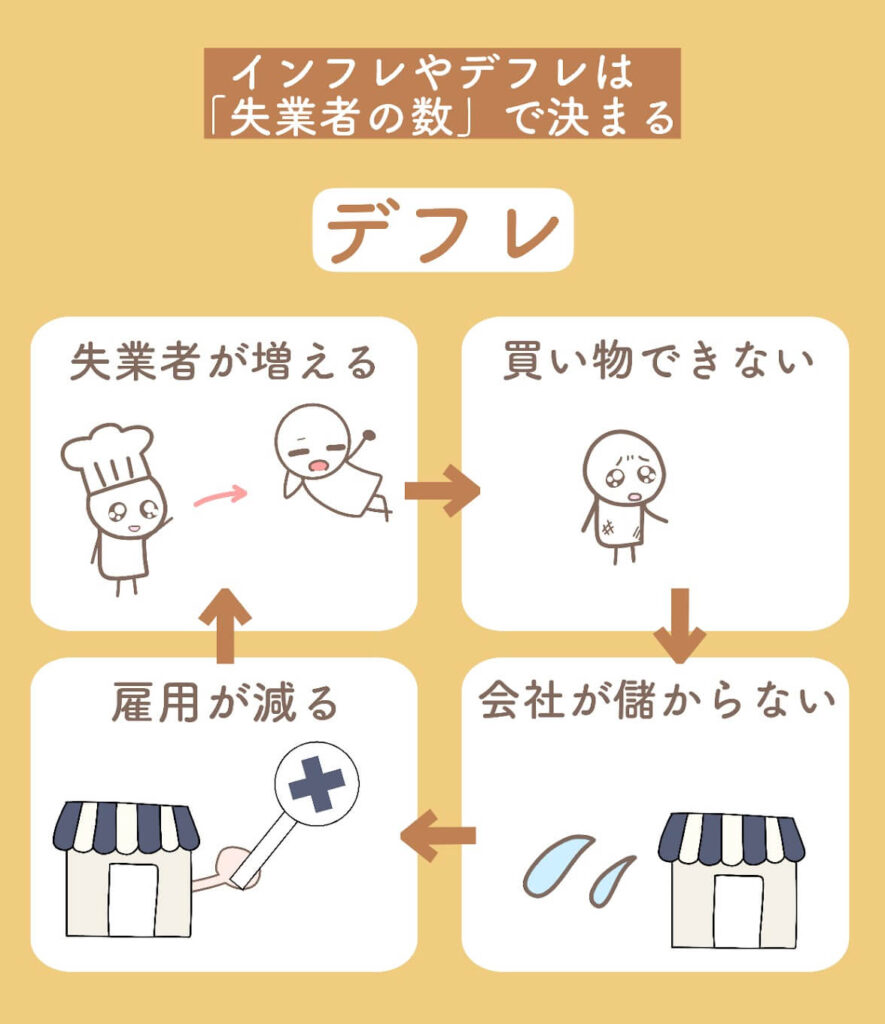
ケインズは、インフレとデフレを操作するには、有効需要を調整したらいいと考えました。
有効需要とは、「欲しいという気持ち」と「お金」がある状態です。
景気が悪い時は、国民は「欲しいという気持ち」はありますが、「お金」がありません。
そのため、国民に「お金」を与えることで、有効需要が増えます。
お金を得た国民は、買い物をします。
買い物をする人が増えたら、物価が上がるのです。
フリードマン
フリードマンは、インフレ、デフレは、国にどれくらいお金があるのかで決まると考えています。
- お金が増えればインフレ
- お金が減ればデフレ
→ お金の量をコントロールするのが一番大事!
国の中にお金が多い時は、物価が上がります。そして、賃金も上がります。
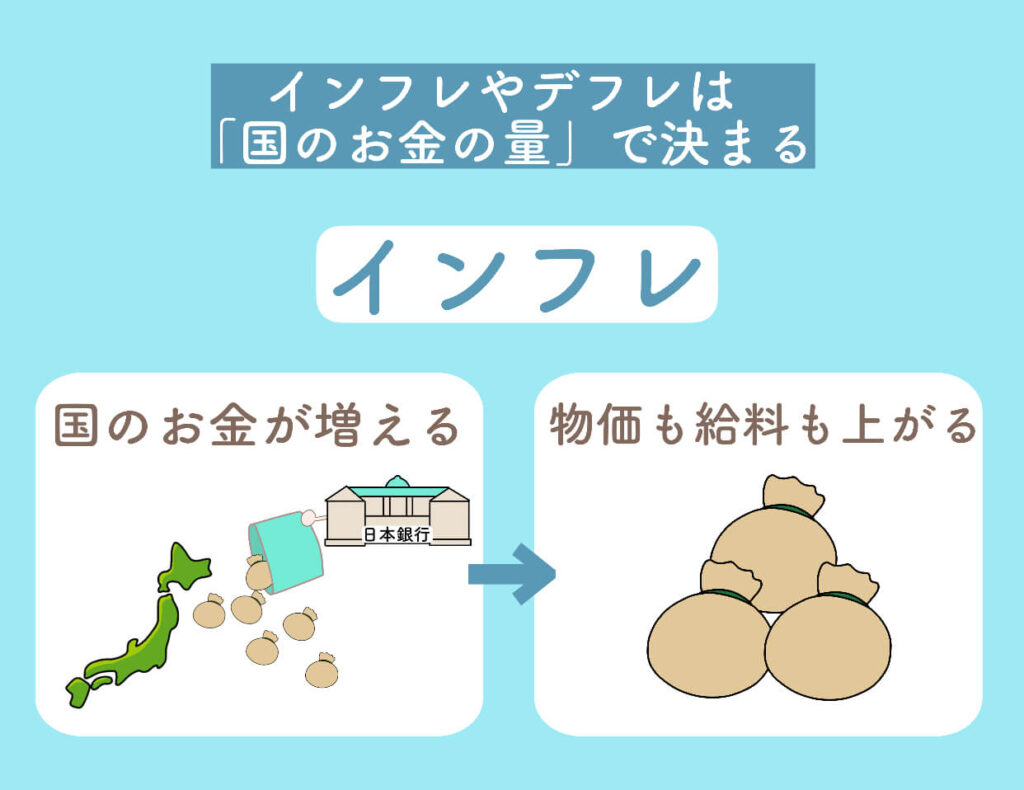
一方で、国の中にお金が少ない時は、物価も下がるし、賃金も下がります。
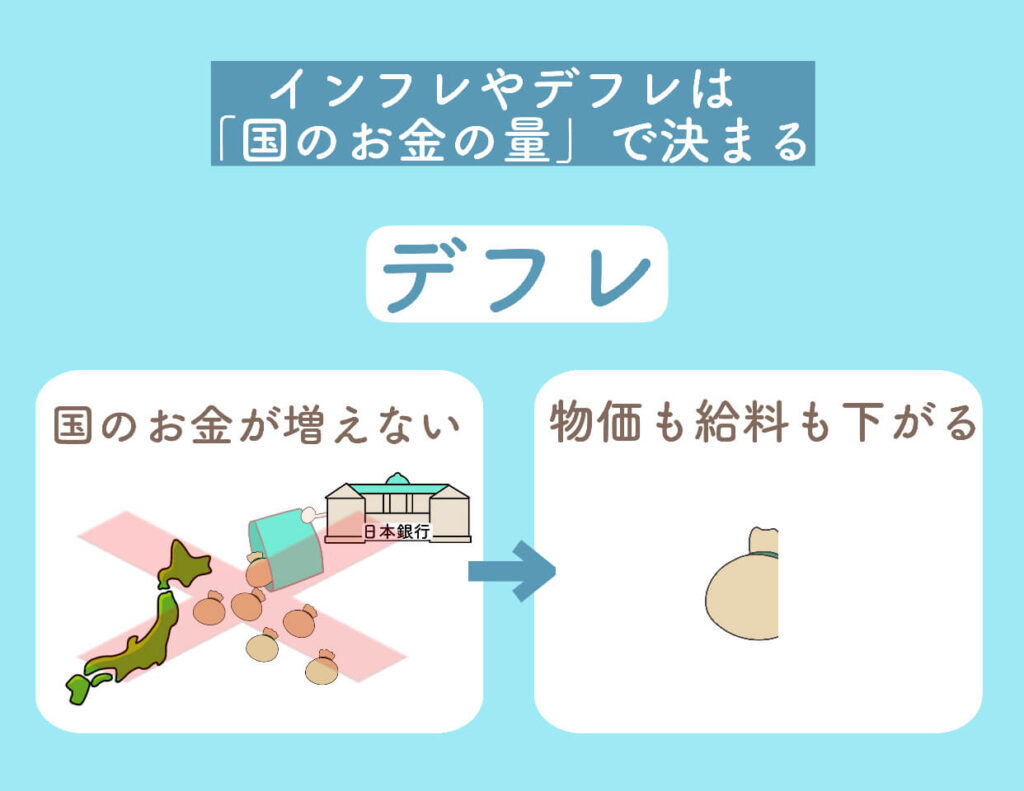
フリードマンは、インフレとデフレを操作するには、世の中のお金の供給量を調整したらいいと考えました。
-
- 世の中のお金の供給量を調整する
- お金の量を一定にしないと自動的にデフレになる
- モノの増加に合わせてお金の量を増やす
- 増やしすぎるとインフレになるので注意が必要
まず、世の中のお金の量を変化させない場合、自動的にデフレになります。
なぜなら、世の中のモノの量は増えているからです。
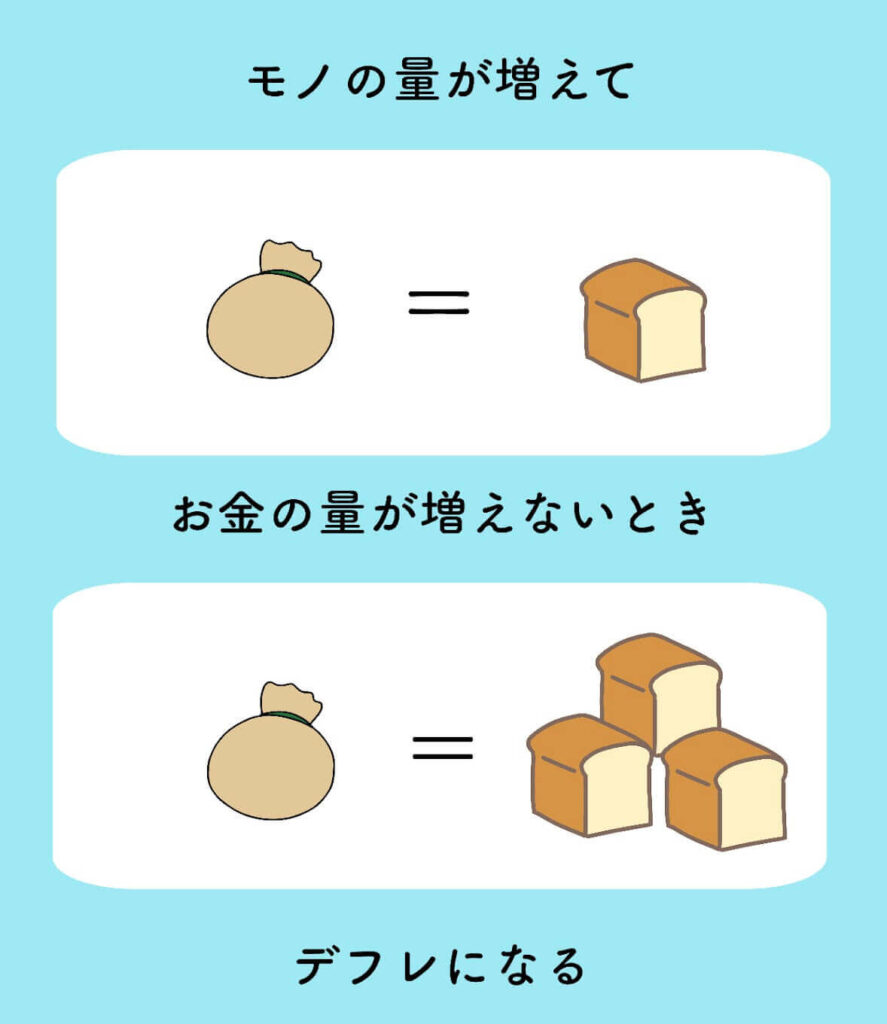
そのため、モノの量が増えるスピードに合わせて、お金の量を増やしてあげる必要があるのです。
しかし、お金を増やしすぎるとインフレになるので、注意が必要なのです。
失業者
次に、失業者についてのケインズとフリードマンの考え方の違いについてです。
ケインズ
ケインズは、失業者が増える理由は、「仕事が足りないから」だと考えました。
ケインズが生きていた時代は、世界恐慌が起きていました。
4人に1人が失業者だったのです。
これほど多くの人が「怠けたいから」失業しているなんて、ありえません。
仕事がないだけなのです。
そのためケインズは、働き口を増やすことが必要だと考えました。
フリードマン
一方で、フリードマンは、失業者は働きたくないだけだと考えます。
働きたいのに働けない人なんていなくて、失業者は、実は「仕事をえらんでいる」だけだと、主張しました。
だから、働き口を増やしたとしても、失業率は、元の水準に戻ると考えました。
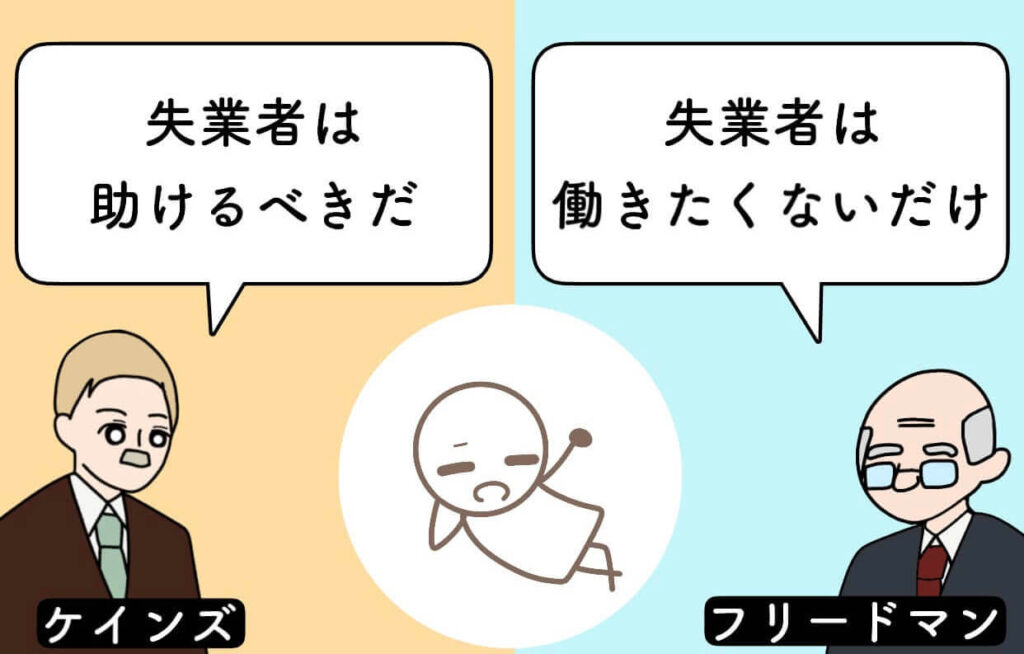
ケインズが失業者を助けようとしたのに対し、フリードマンは、失業者は放置するべきだと考えました。
物価を一定に保つ方法
物価は一定の方がいいです。
物価を一定にするためには、なぜ、物価が上がったり下がったりするのかを理解する必要があります。
物価が上がったり下がったりする理由は、分かっていません。
二つの説があります。
・貨幣数量説
・需要過不足説
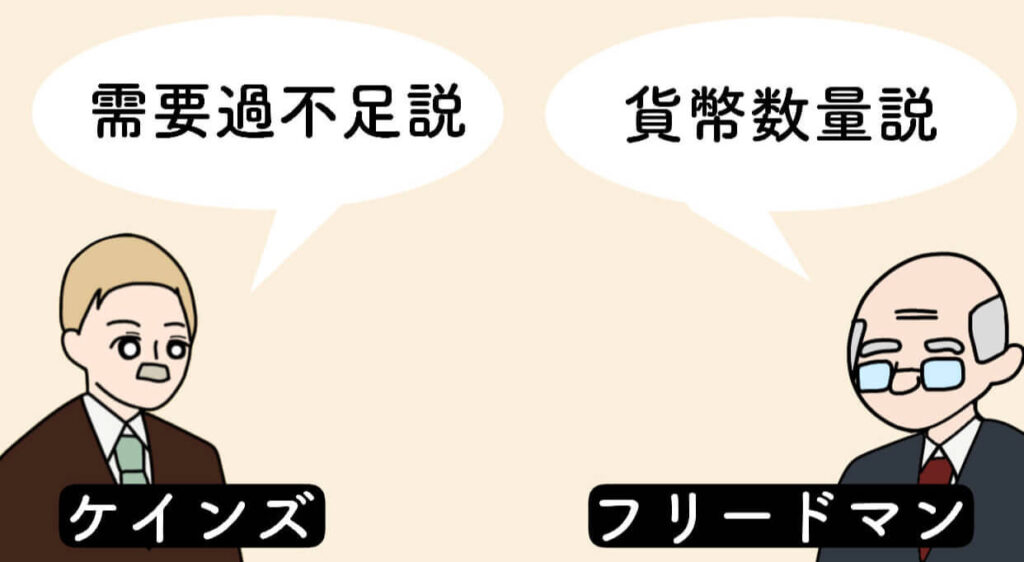
ケインズ
需要過不足説を信じているのはケインズです。
ケインズは、お客さんが商品を買ってくれる時は物価が上がり、商品を買ってくれない時は物価が下がる、と考えました。
もし、パン屋さんにパンが一つしかなくて、パンを買いたいお客さんがいっぱいいる時は、お客さんがパンを奪い合います。
このように商品をお客さんが奪い合う状況の時は、パンは高くても売れるようになります。
そのため、パン屋さんはパンの値段を高くします。
買う人が多いと、物価が上がります。
買う人が少ないと、物価が下がります。
需要が過剰なのか、不足してるのかで、物価は変化します。
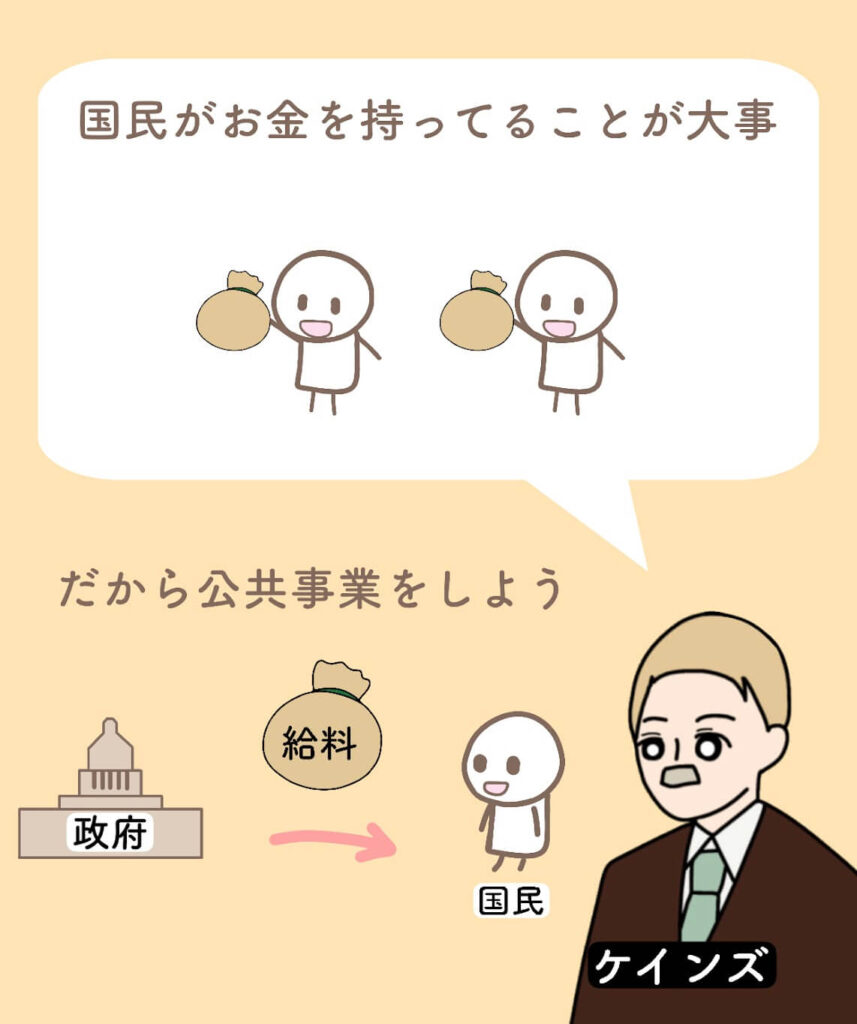
それが需要過不足説の考え方です。
フリードマン
一方で、フリードマンが信じたのは、貨幣数量説です。
フリードマンは、少しずつお金を刷るだけでいいと言っています。
お風呂に水を入れると、水位は上がります。
お風呂の水を減らすと、水位は下がります。
物価もこれと同じです。
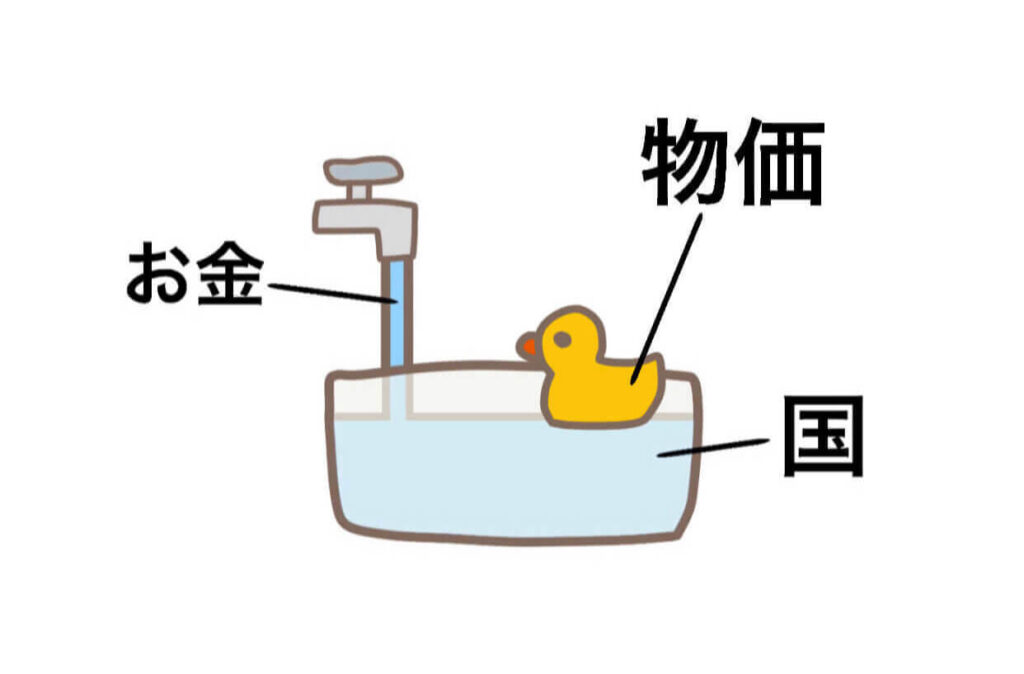
国にお金を入れると、物価が上がります。
国のお金を減らすと、物価が下がります。

国にお金を入れると、物価が上がります。
つまり、お客さんが買えるものの量は減ってしまいます。
インフレになると、生活が豊かにならないのです。
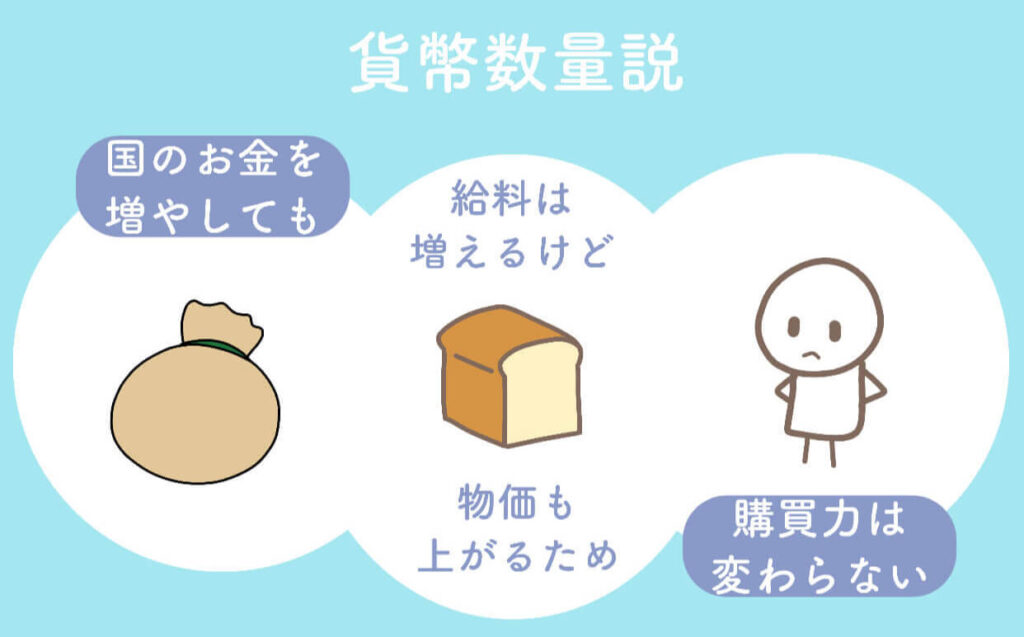
だから、国のお金の量をむやみに増やしてはいけない、とフリードマンは主張しました。
まとめ:どちらが正しいの?
ケインズとフリードマン、どちらの考え方も、それぞれの時代の問題に対する答えでした。
- ケインズは「不景気(デフレ)」をどうするかを考えました。
- フリードマンは「インフレ」をどう防ぐかを考えました。
つまり、どちらが「正しい」というより、時代や状況によって使い分ける必要があるのです。