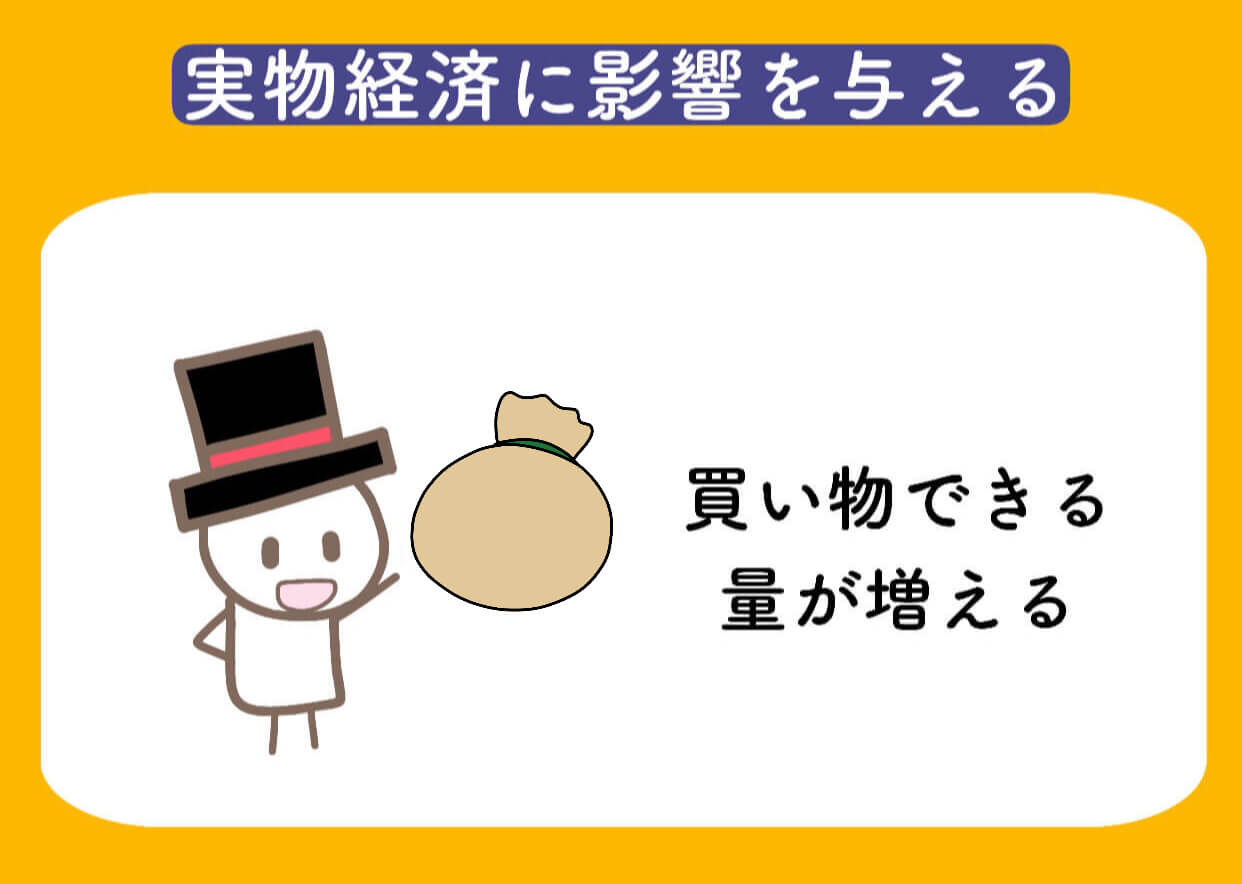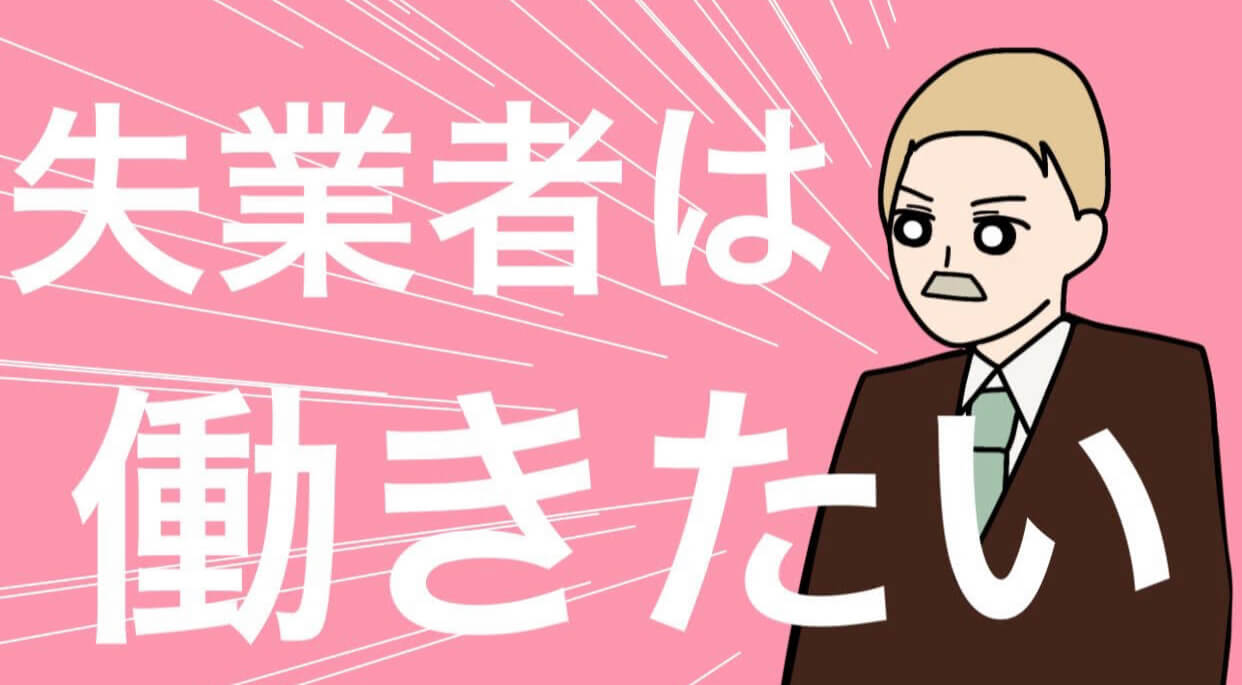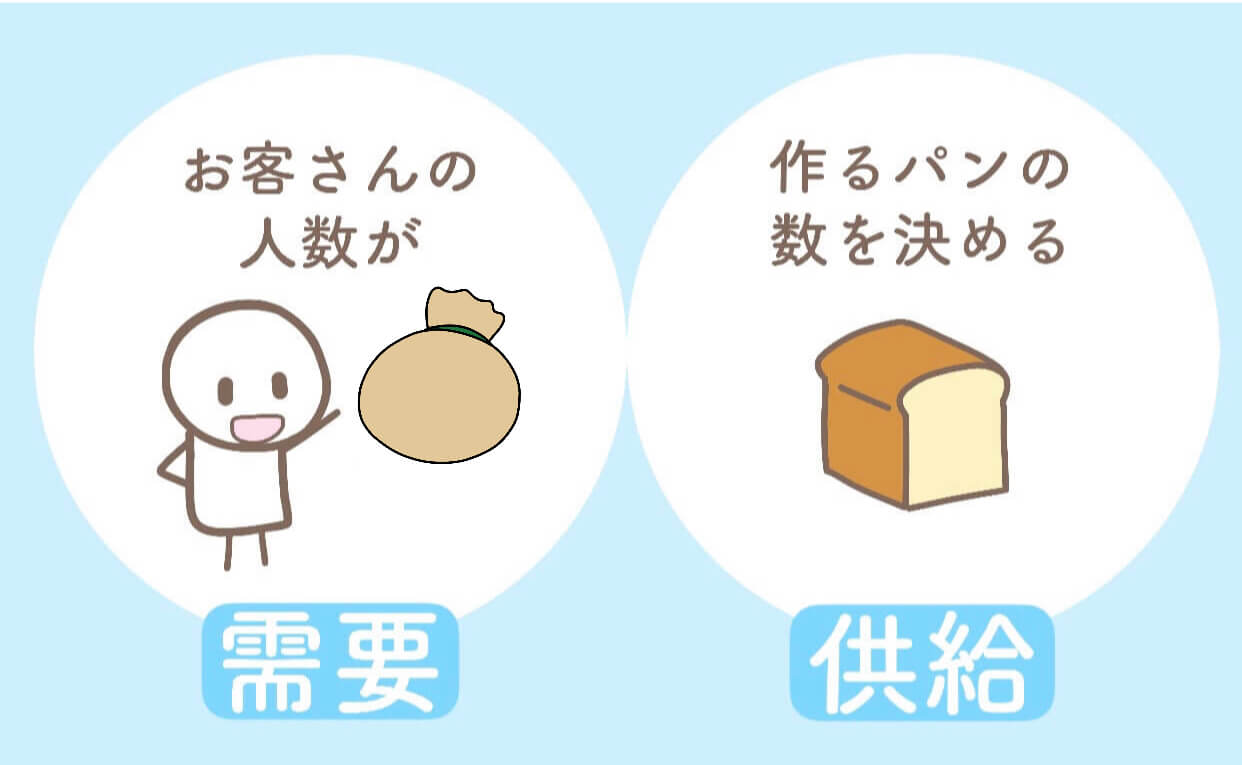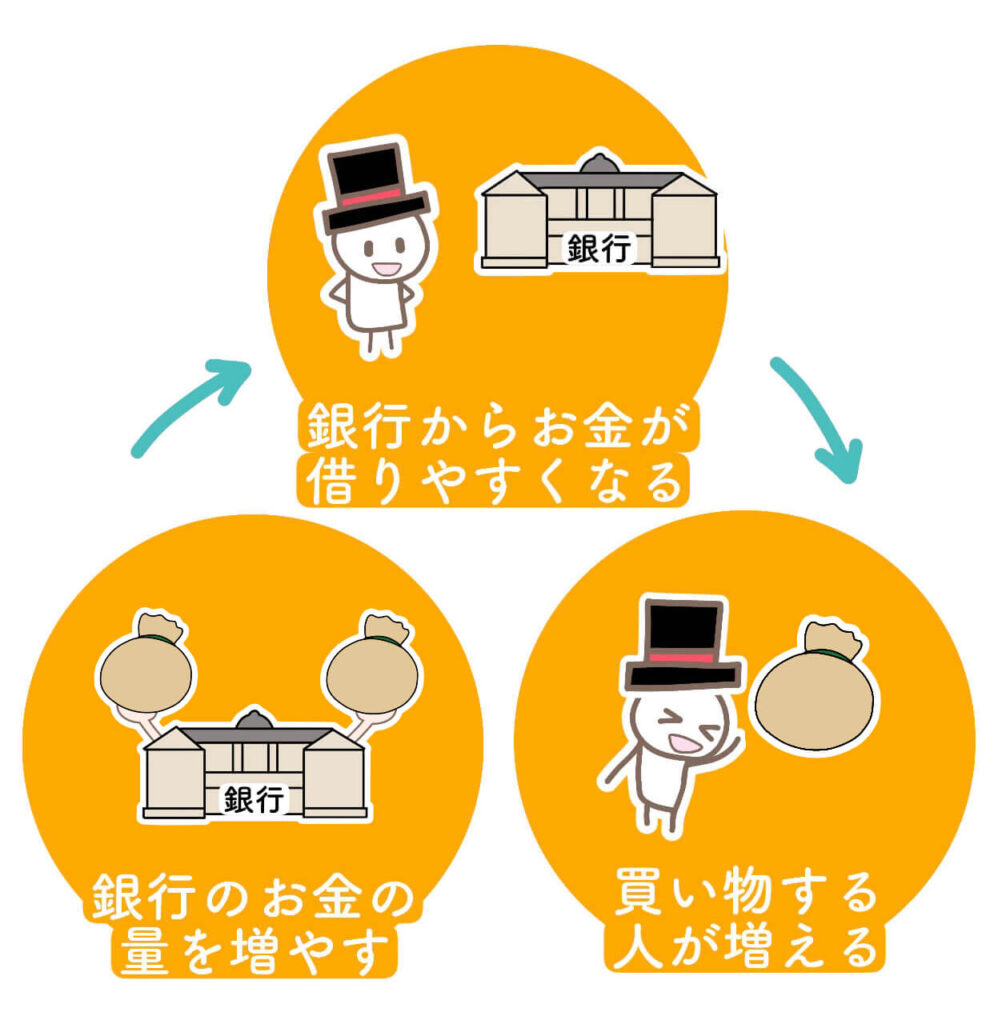
銀行のお金の量を増やす
まず、貨幣供給を増やすことについてです。
貨幣供給量を増やすのは、中央銀行です。
中央銀行が、銀行のお金の量を増やします。
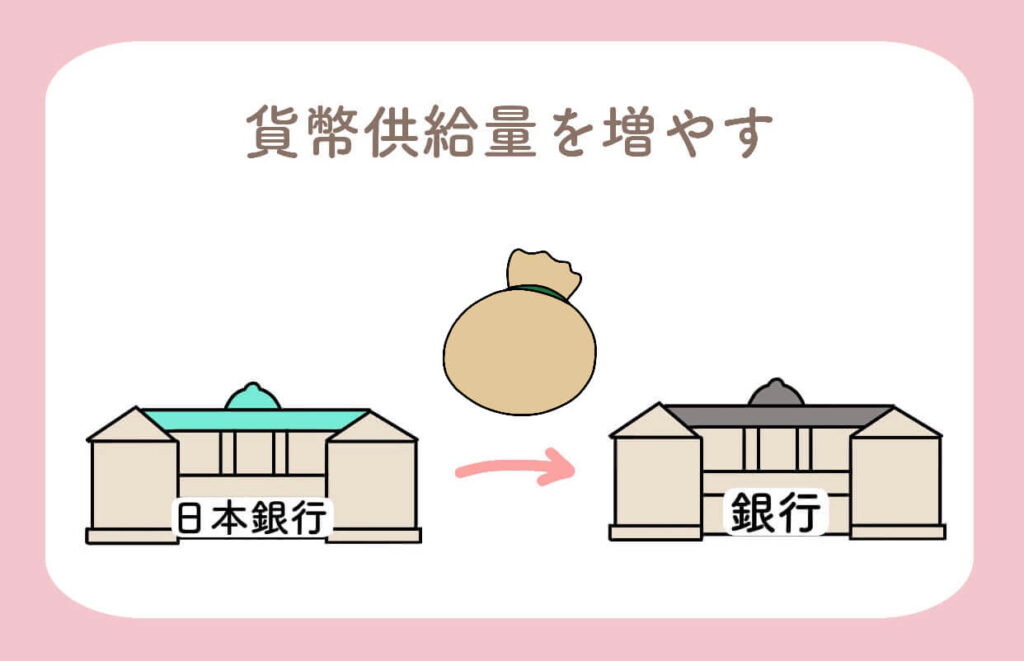
「貨幣供給を増やす」というのは「銀行のお金の量を増やす」ということです。
そうすると、銀行は、利子率を低くします。
銀行からお金を借りやすくなる
銀行が利子率を低くする理由は、お金をたくさん持っているからです。
銀行にお金がたくさんある時は、国民に借りてもらいたいので、利子率を下げるのです。

銀行のお金の量が増えると、利子率が下がります。
そして、利子率が下がると、お金が借りやすくなります。
つまり、お金を借りる人が増えます。

買い物する人が増える
銀行の利子率(りしりつ)が下がると、お金を借りるのがかんたんになり、たくさんの人や会社がお金を借りたくなります。
では、どんな人が借りるのでしょうか?例えば
・車を書いたい人
・家を買いたい人
・会社やお店をやっている人
新しいお店を出したり、機械を買ったりするために、お金が必要になります。
このように、会社やお店などが、自分たちの仕事をよくするために、お金を使うことを民間投資と言います。
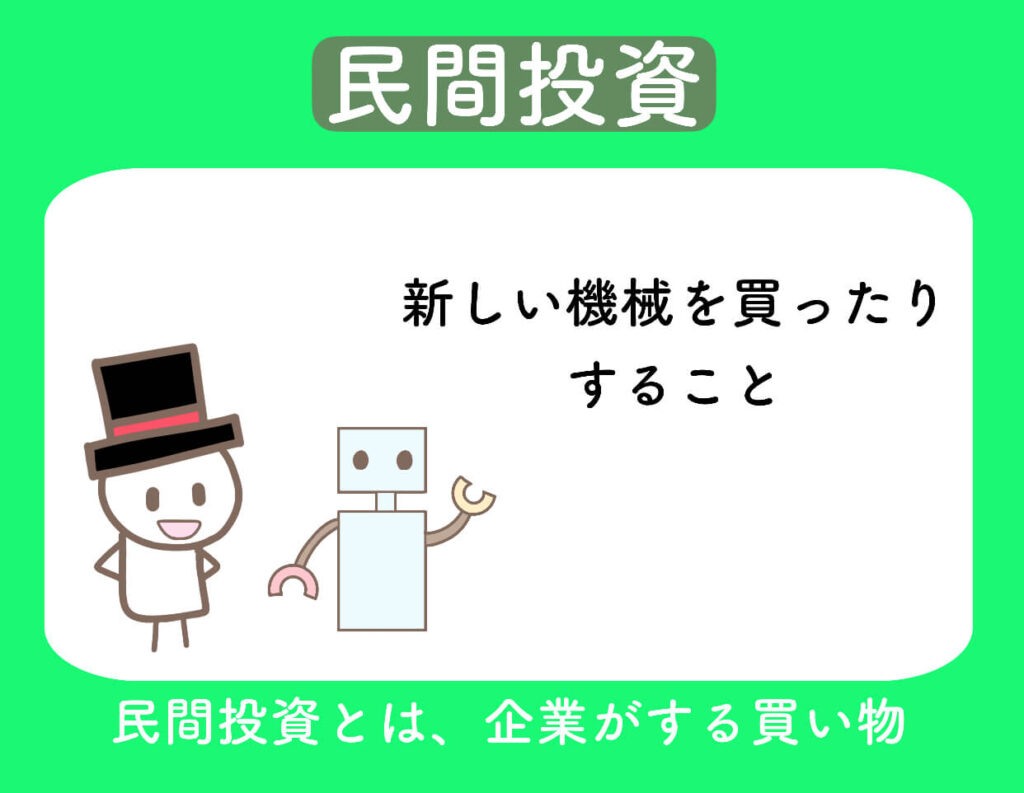
会社やお店は、銀行から、お金を借りて、民間投資をします。
民間投資は、景気を活気付けてくれます。
なぜなら、誰かが買い物をすれば、それを売った人が儲かるからです。
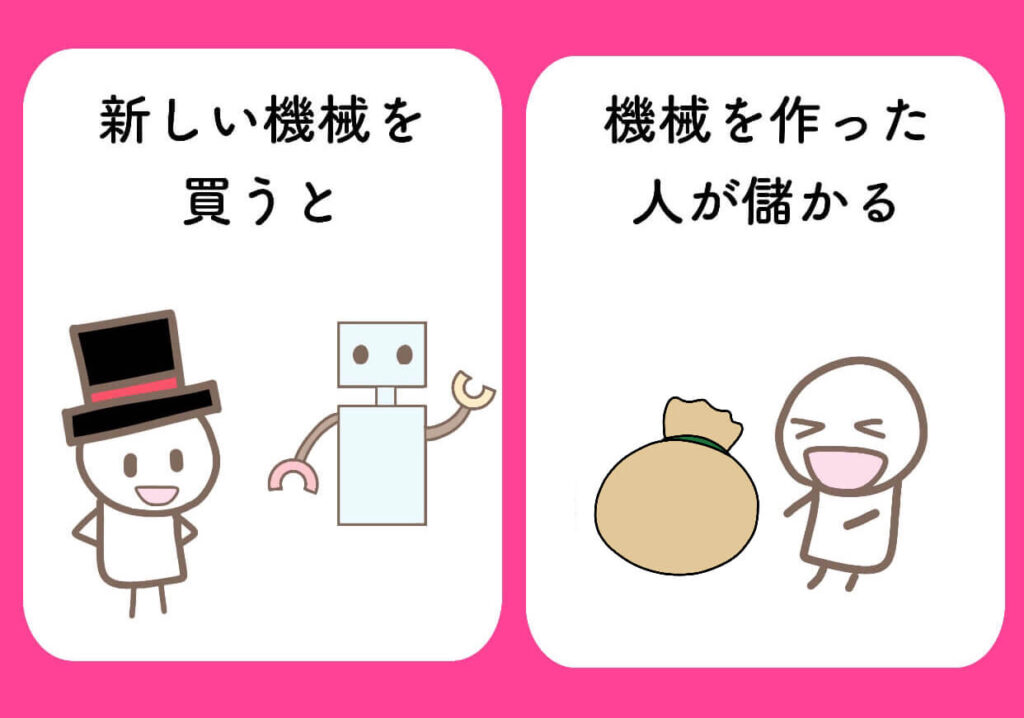
銀行が、どんどん国民にお金を貸して、世の中に出回るお金の量を増やすことを「貨幣供給を増やす」と言います。
実物経済
実物経済とは、モノやサービスの生産・売買・消費など、実際に人々が生活や仕事の中で行っている経済活動のことです。
つまり、「お金」そのものではなく、お金を使って何が動いているかに注目するのが実物経済です。
「実物経済に影響を与える」ということは、「買い物できる量が増えたり減ったりする」ということです。
また、今回は、ケインズは「貨幣供給量」が増えると、「買い物の取引量が増える」というニュアンスでこの言葉を使っています。
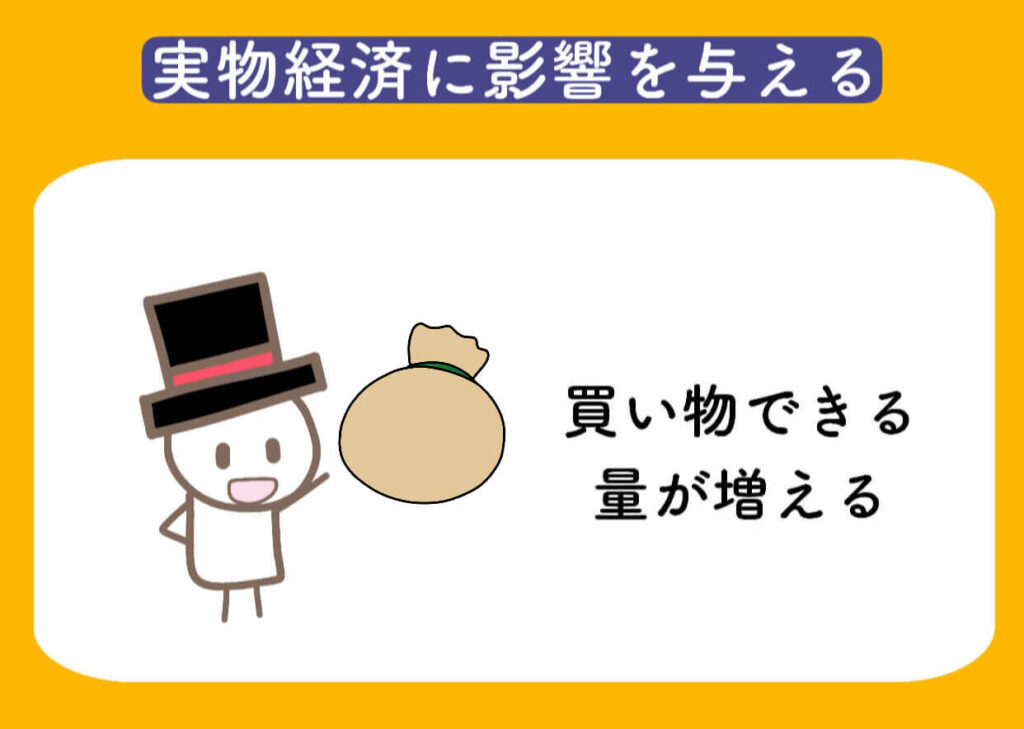
貨幣供給が増えると、国民の「買い物できる量」は増えます。
人々が、活発に、モノの売り買いをするようになります。
つまり、国のお金が増えたら、買い物をする人が増える、ということです。