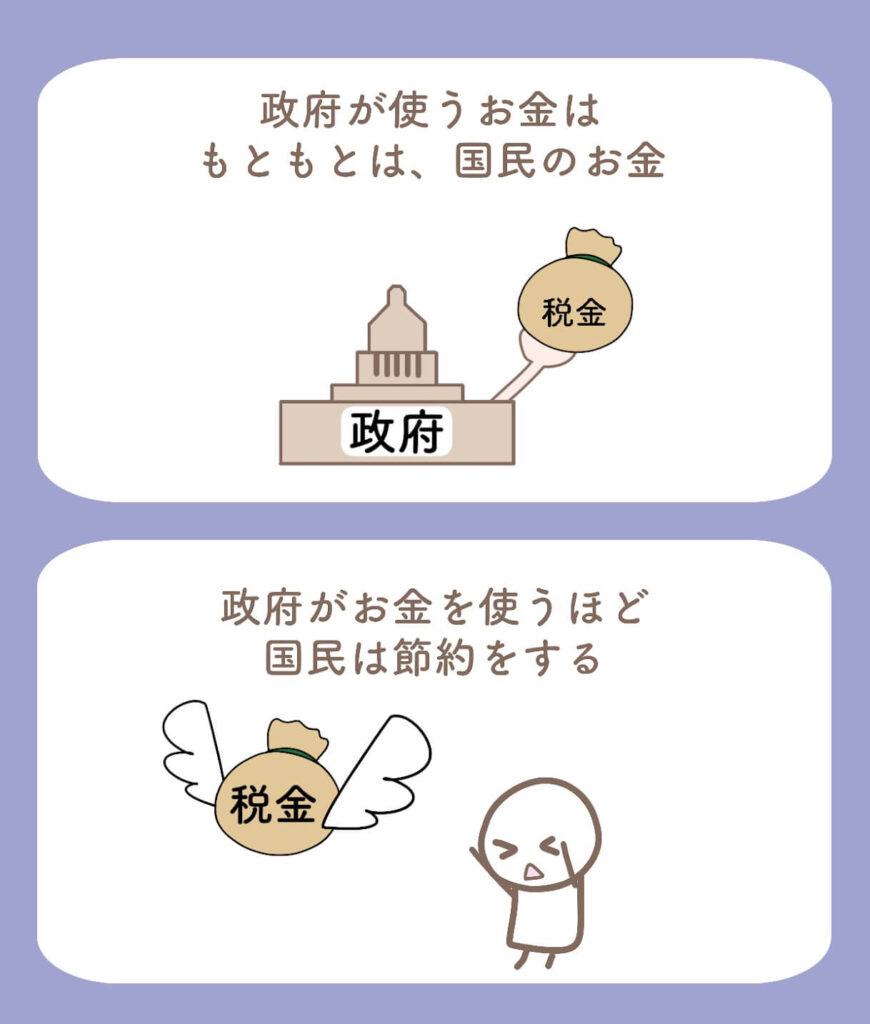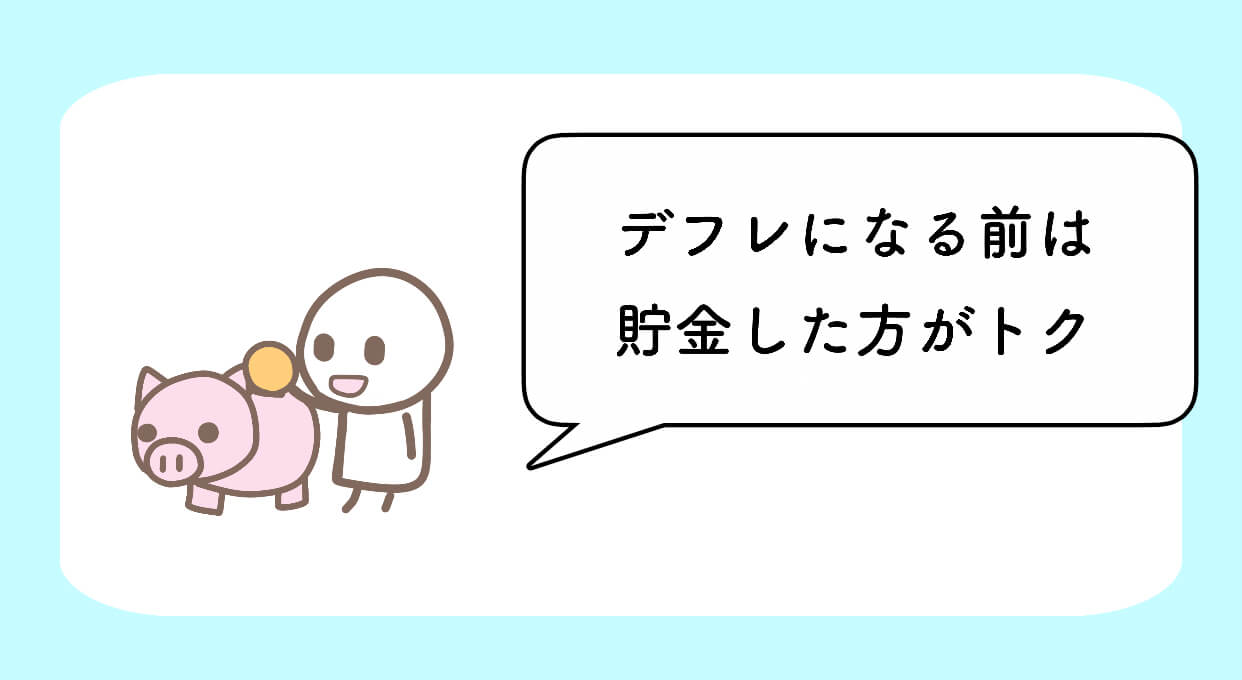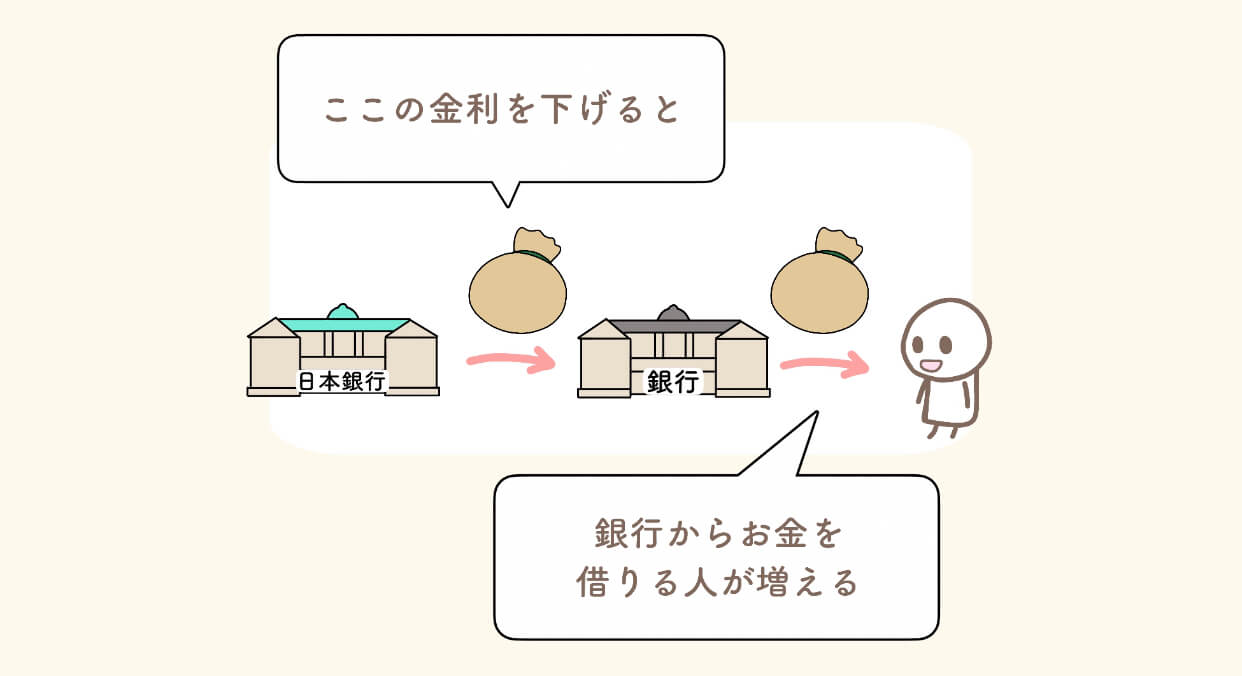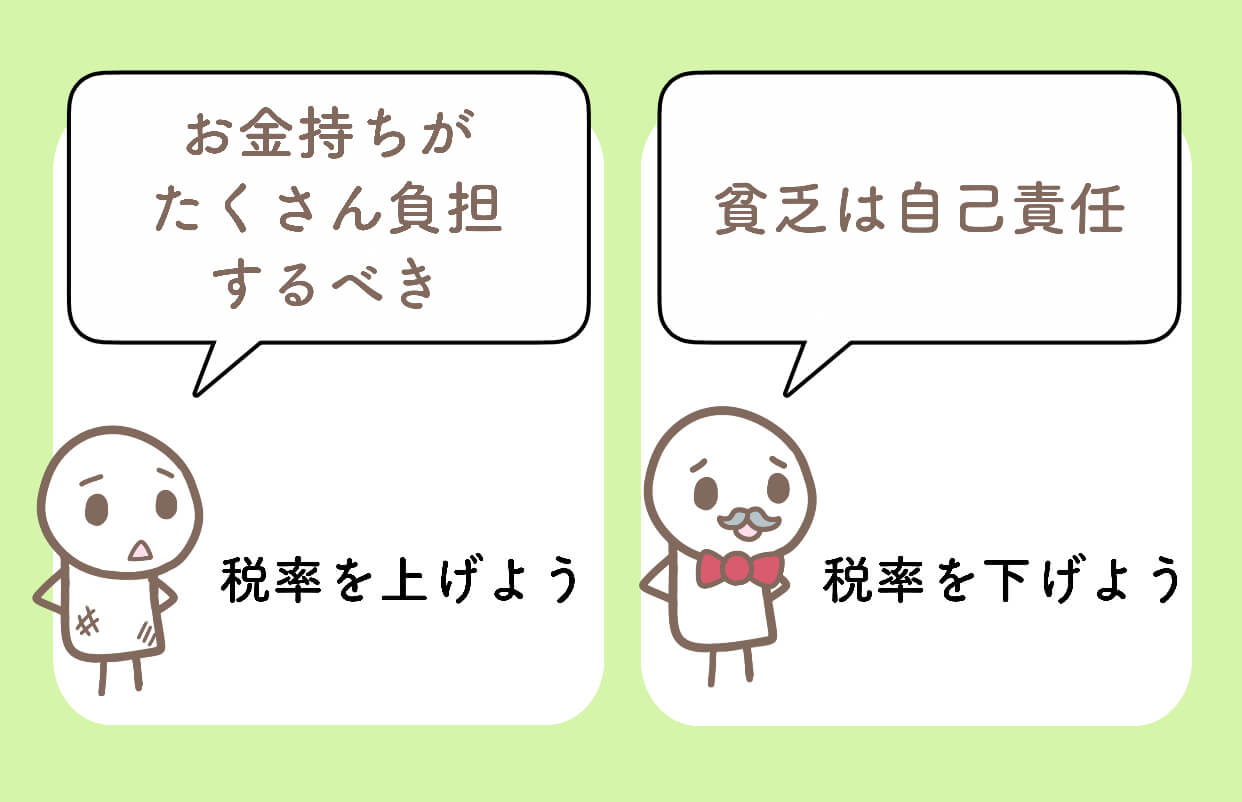「異次元」とは、「すごく」という意味です。
「緩和」とは、「国内に流れているお金の量を増やす」という意味です。
つまり、「すごく国のお金を増やす」ということです。
「量的緩和」も同じ意味です。
安倍政権は、日本にあるお金の量を「2倍」にしました。
国内に流れているお金の量をめちゃめちゃ増やしました。
この記事では、その狙いと結果について書きます。
お金を増やす
国のお金の量を増やした理由は、デフレから脱却したかったからです。
「脱却」とは、「悪いものから抜けだす」という意味です。
「デフレの状況を変えたい」と思っていたのです。
ちなみに、「デフレ」の対義語は、「インフレ」です。
「デフレを脱却したい」とは「インフレになってほしい」と同じ意味です。
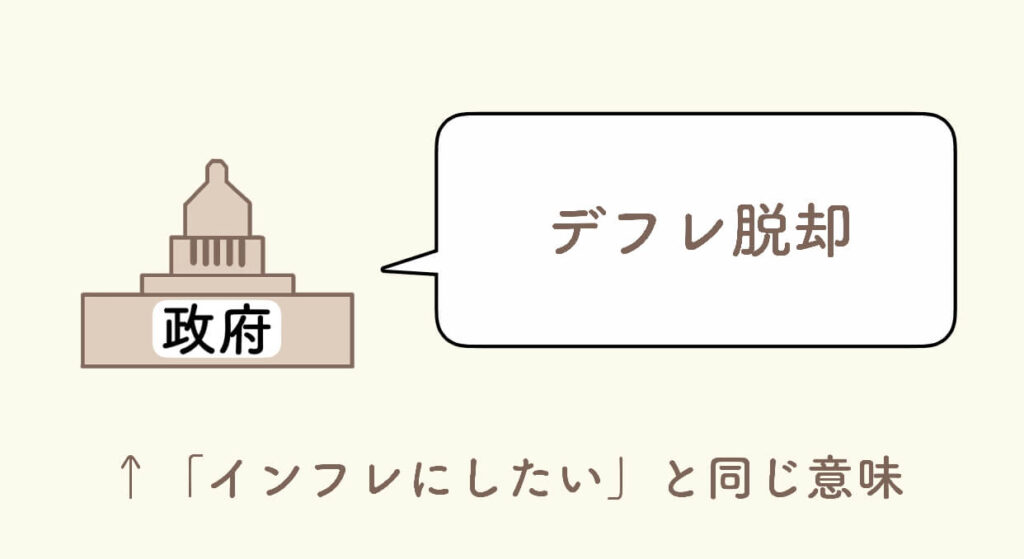
安倍首相は、「日本をゆるやかなインフレにします」と繰り返し主張していました。
インフレにするための方法は、「量的緩和」です。
日本は、2013年から、量的緩和をしてきました。
つまり、国内のお金の量を増やしてきたのです。
量的緩和
量的緩和の目的は、デフレを止めることです。
当時の日本は物価がどんどん下がって、給料も下がってしまっていました。
それはよくないということで、安倍政権では「デフレを止めて、みんなの給料を高くする」という目標を掲げていました。
国民にお金が行き渡るようにする方法は、お金をジャンジャン刷ることです。
お金をジャンジャン刷ることを、量的緩和と言います。
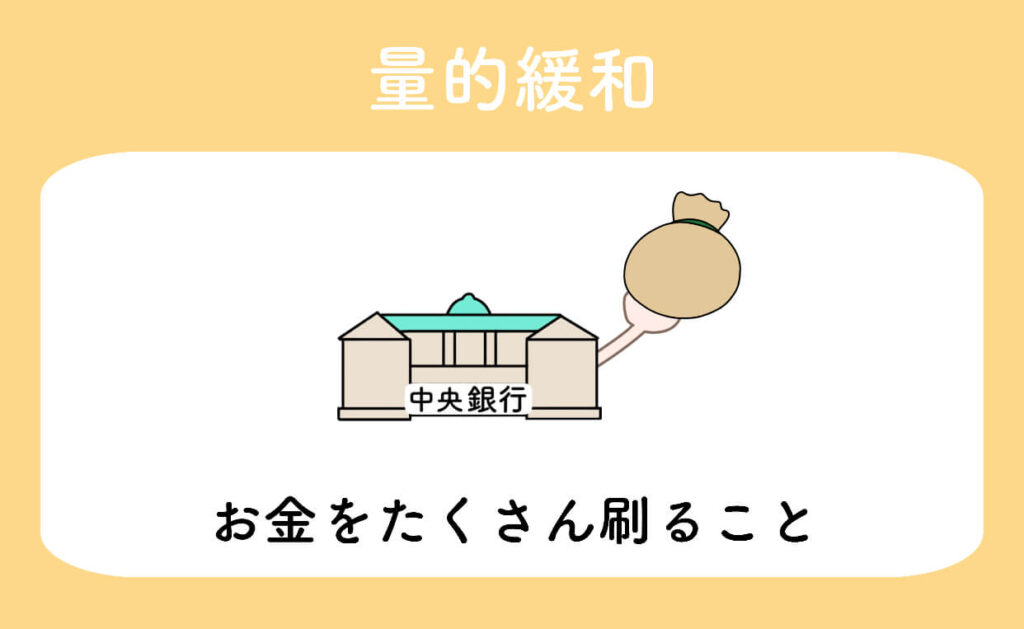
国のお金が増えると、景気が良くなる理由
量的緩和というのは、国のお金を増やすことです。
国のお金が増えると、景気が良くなります。
その理由は、みんなが一斉にお金持ちになれば、お店のモノが高くても売れるようになるからです。
すると、お店が儲かります。
また、お店のモノの値段が高くなります。
それを予想すると、人々は急いで買い物をするようになります。
インフレになると、買い物できる量が「減る」からです。
これから値上がりするなら、急いで買い物をした方がいいのです。
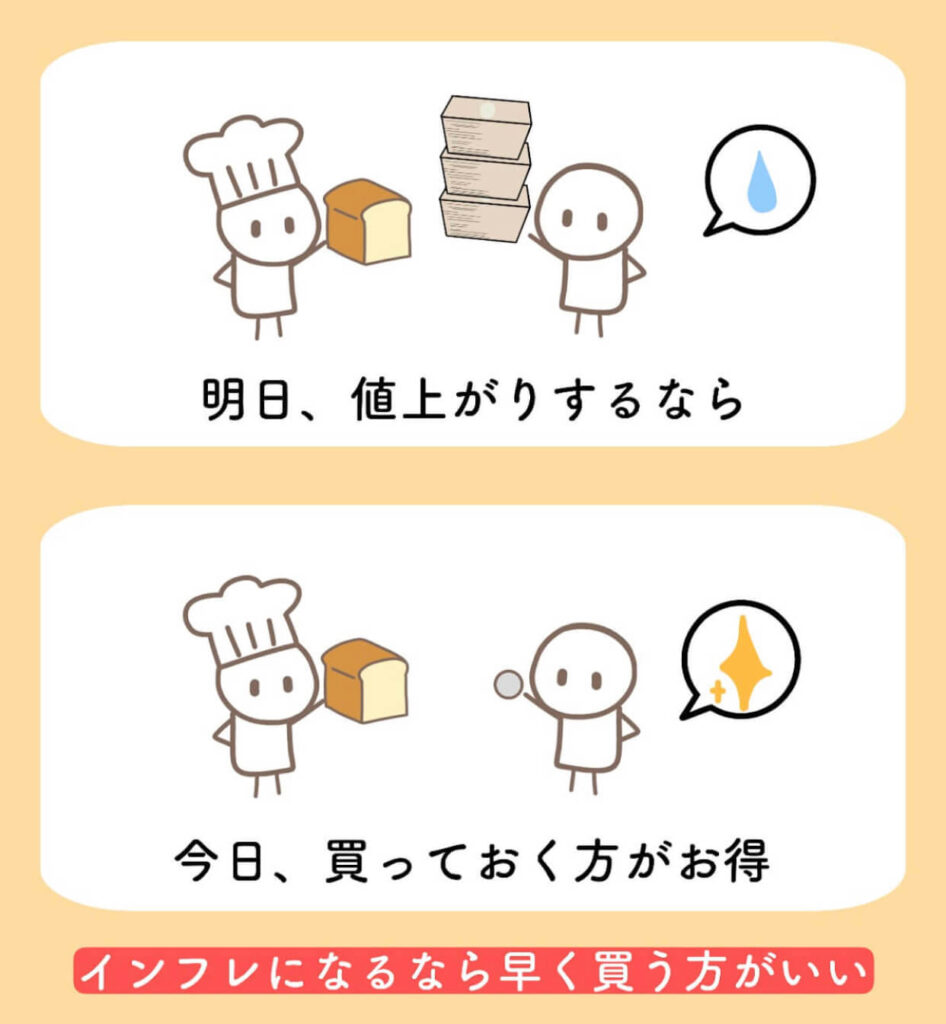
物価が上がることを「インフレ」と言います。
お店の商品の値段が上がるので、買い物できる量は減ります。
インフレになるなら、早く買い物をする方がいいです。
例えば、私が子どもの頃は、1000円でうまい棒が100本買えました。
しかし、いまは、インフレになってしまったため、100本も買えなくなってしまいました。
今から振り返れば「安かった頃に、たくさん食べておけばよかったなー」と思います。
急激に、インフレになっている場合は、より早く買い物をした方がいいです。
値段が高くなる「前に」買いだめをすると、おトクなのです。
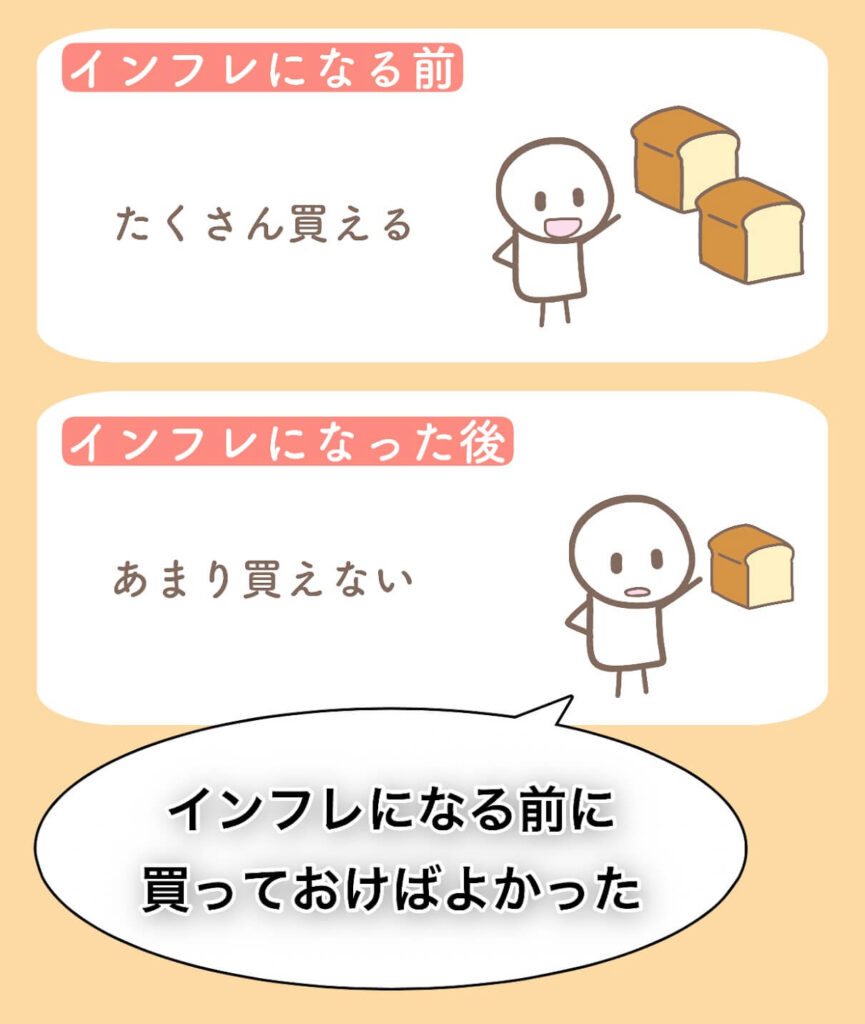
買おうと決めているものがある場合は、値上がりする前に買う方がいいです。
値上がりした後に「インフレになる前に買っておけばよかった〜」と後悔したくありません。
買いたいものがあるから、インフレになる「前に」前倒しで買ってしまうほうがおトクです。
さらにいうと、インフレになると言うことは、今まで貯金をしてきた人は、貯金してきた額の価値が下がってしまうと言うことです。
それなら、お金の価値が下がる前に、モノと交換してしまう方がいいわけです。
このように、銀行がお金をたくさん刷れば、インフレが予想されるので、みんなが焦って、買い物するようになるはずです。
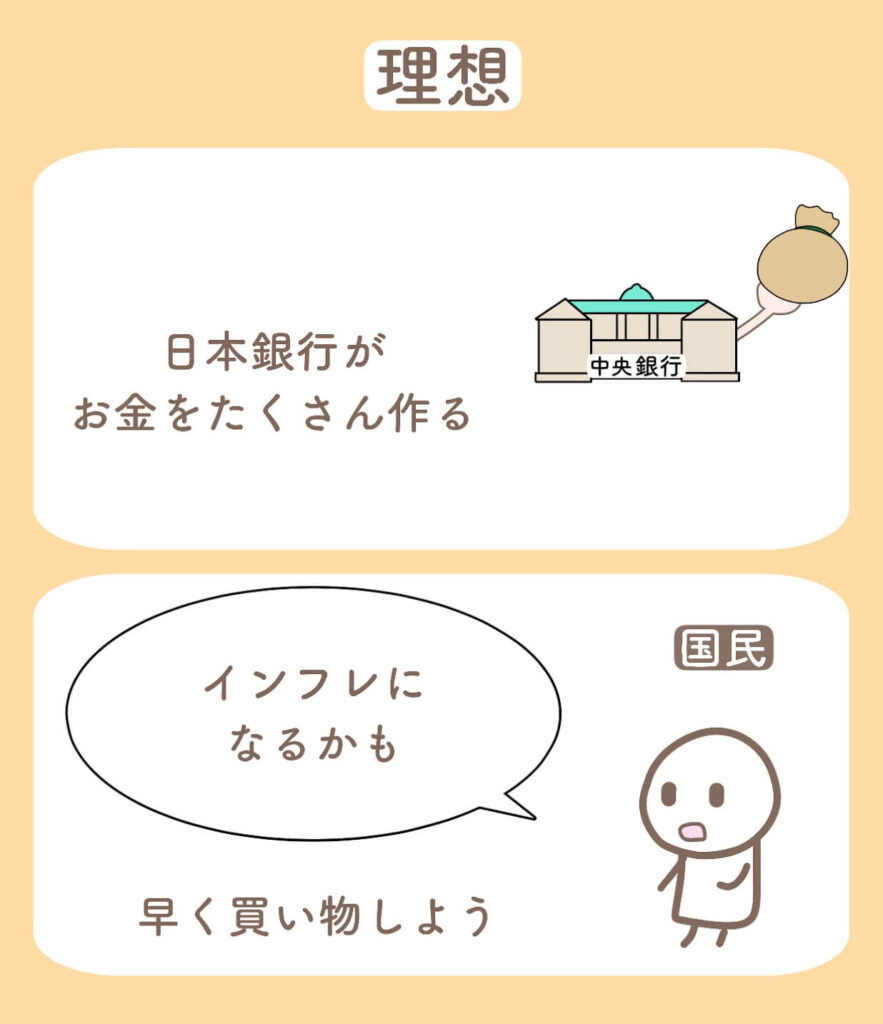
そのため、アベノミクスでは、わざと、インフレを作ろうとしました。
安倍政権は「日本銀行がたくさんお金を刷れば、人々は焦って買い物をするだろう」と考えていました。
お客さんが焦って買い物をすると、モノが売れるようになります。
そうして、経済が良くなると予想されていました。
結局どうだったのか
アベノミクスは、結局どうだったのでしょうか?
結論から言うと、あまりモノが売れるようにはなりませんでした。
その理由は、日本の国民は、お金を持っていても、使わないからです。
ここでいう国民とは、個人だけでなく企業も含まれます。
日本の企業は、お金を持っているのに、お金を使っていないのです。
お客さんがお金を使わないので、お店は儲からず、モノの生産も増えませんでした。
お客さんがお金を持っていても、生産量が増えなければ、経済が発展しないのです。
日本銀行がジャンジャンお金を刷っても、国民は「早く買い物しなきゃ!!」とはならなかったのです。
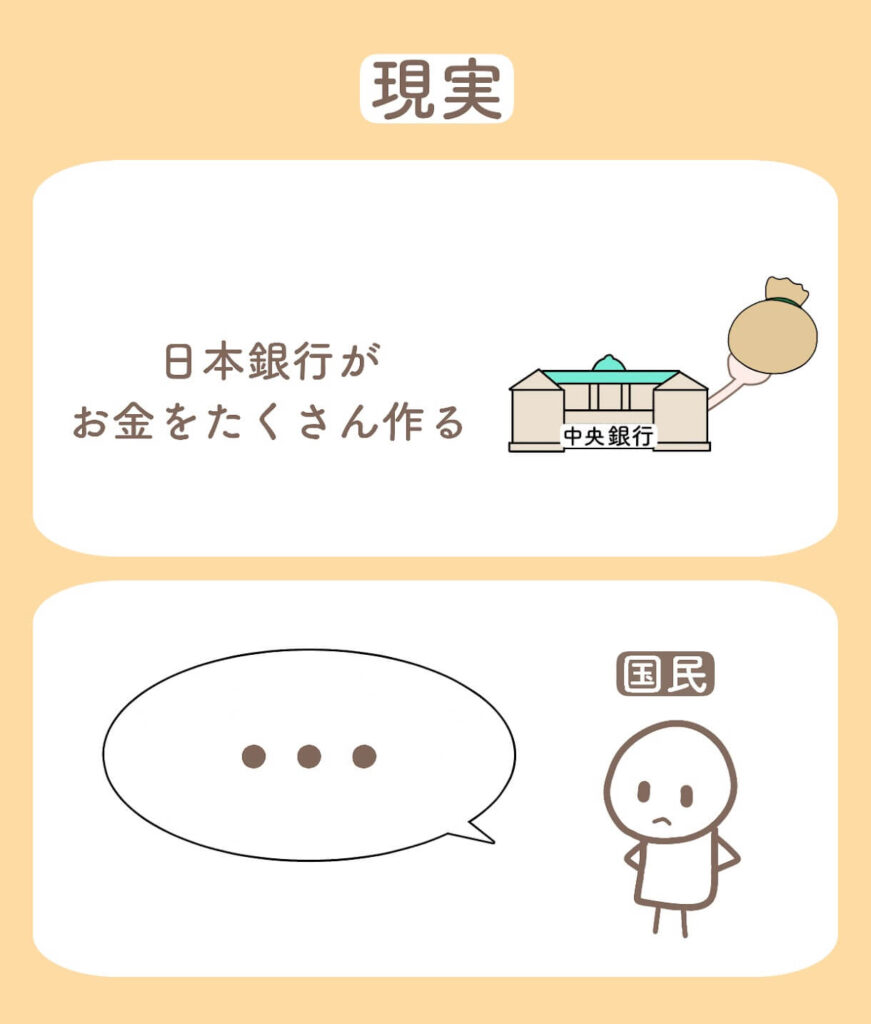
2014年の日本は、お金の量は2倍になったのに、物価は上がりませんでした。
さらに、実質賃金は下がり、経済成長率はマイナスでした。
景気がよくならなかった理由
景気がよくならなかった理由は、悪い未来を予想する人が多かったからです。
これから、経済は悪化するだろうと予想している時は、人々はお金を使いません。
貯金をしてる方が安心だからです。
また、デフレが悪化すると、予想している時は、貯金をした方がおトクです。
デフレとは、モノの値段がどんどん下がっている状況です。
これは、言い換えると、貯金してるお金の価値が増えるということなのです。
買い物をするなら、デフレになった「後」に買い物をした方がお得です。
将来、日本がもっとデフレになるなら、「今は買い物を控えよう」と考える人が増えます。
買い物をしないで、貯金をした方が良いのです。
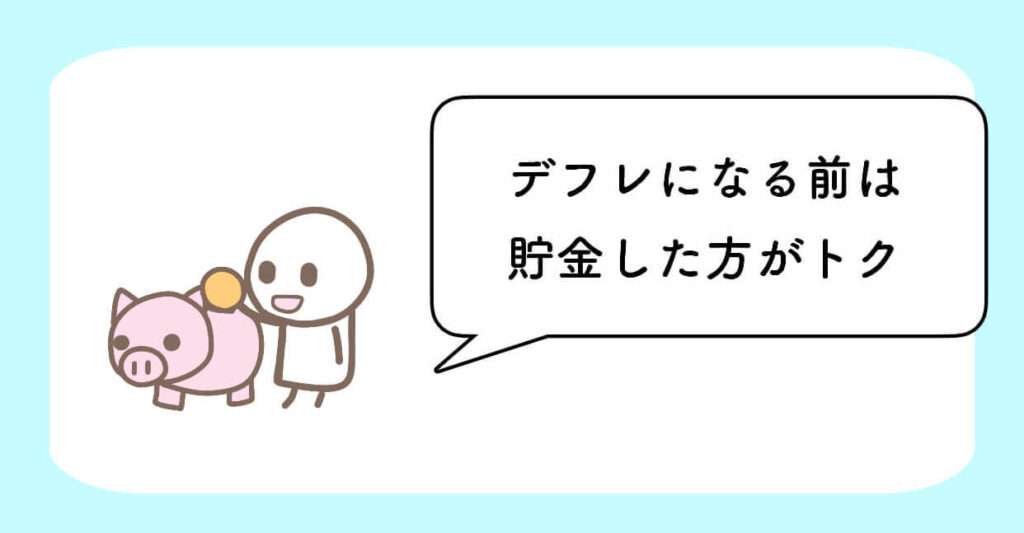
「日本がインフレになる見込みはない」と、投資家が判断すれば「お金を借りて工場を大きくしよう」という気持ちにならないのです。
デフレが解決しない理由
このように、デフレが解決しないケースもあります。
例えば、お金を借りてくれる人がいない時です。
どんなに金利を下げても借り手が現れず、お金が使われない状態です。
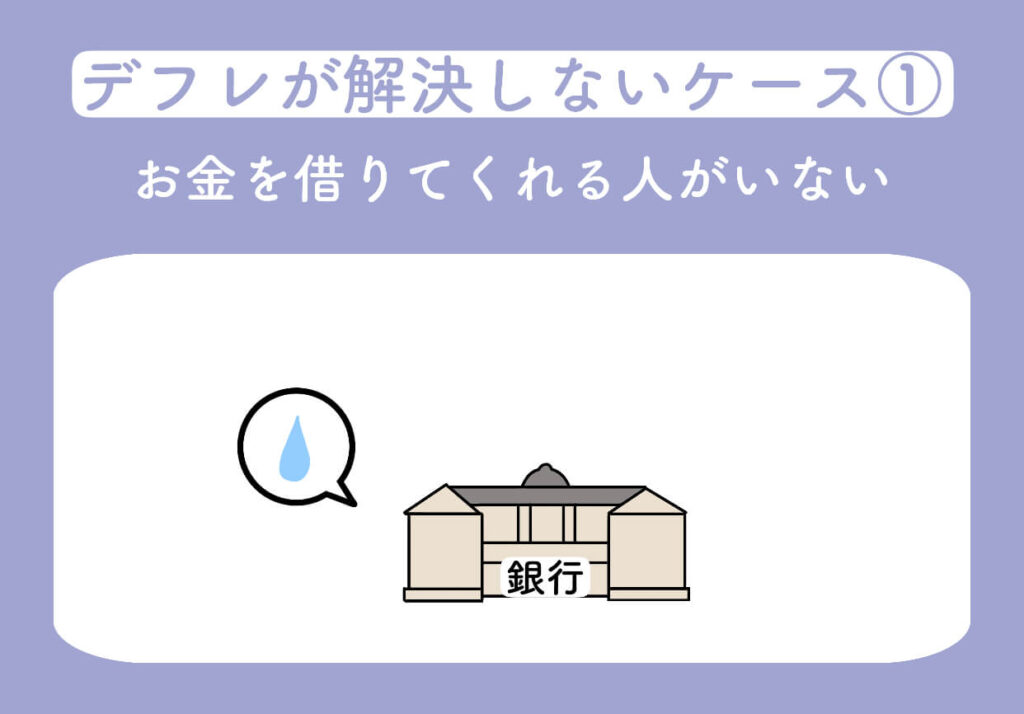
他には、国内産業に活力がない、購買意欲をそそるヒット商品がないことです。
商品を買ってくれる人がいないと、企業は儲かりません。
企業が儲からないと、従業員の給料も上がらず、景気が良くならないのです。
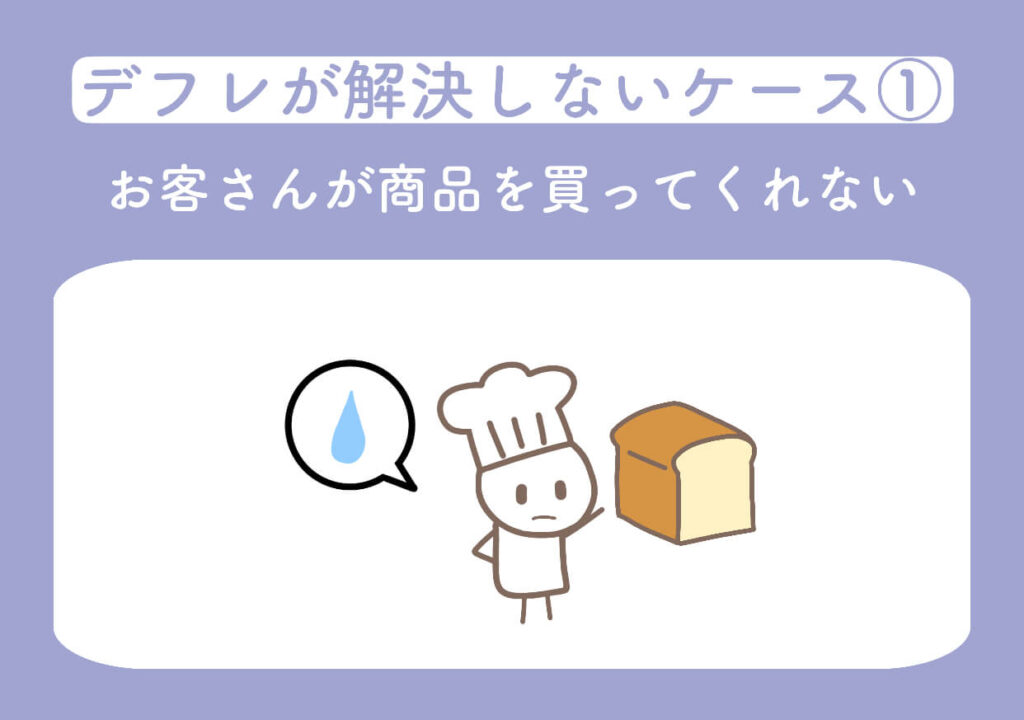
こうした状態においては、金融政策だけでは、不況を解決できません。
そんな時に行うのが、財政政策です。
財政政策
財政政策とは、国民に給料を与えるために、政府が仕事を作り出す事です。
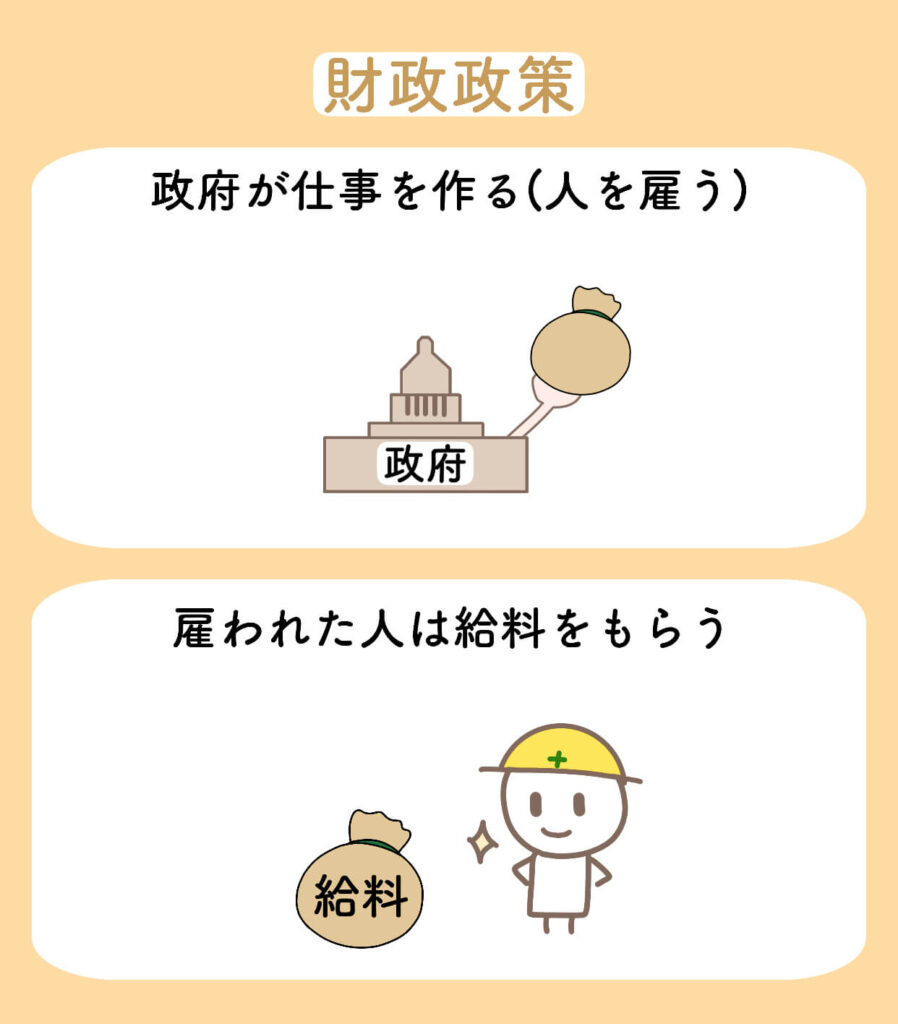
ケインズ経済学では、デフレの原因は、国民の給料が低すぎることだと考えられています。
そのため、政府が支出をして、建設業者の人に給料を与えたりする中で、経済を回すべきだと考えられています。
しかし、建設業者が儲かっても、建設業者の人たちが、ガンガンお金を使わないと、効果は一時的なものになってしまいます。
もし、みんながお金を使ったら、景気が良くなります。
しかし、みんなが貯金してしまうと、景気が良くならないのです。
また、財政政策をするのには、お金が必要です。
お金を用意するために「国債」という借金をします。
国債を発行しすぎると、大きな借金を抱えてしまいます。
つまり、未来の子どもたちが払う税金が増えるということです。
それに、政府が使うお金は、元々は国民のお金です。
税金が増えたら、その分、国民は節約するようになります。
政府がお金を使っても、その分、国民がお金を使わなくなることもあるのです。