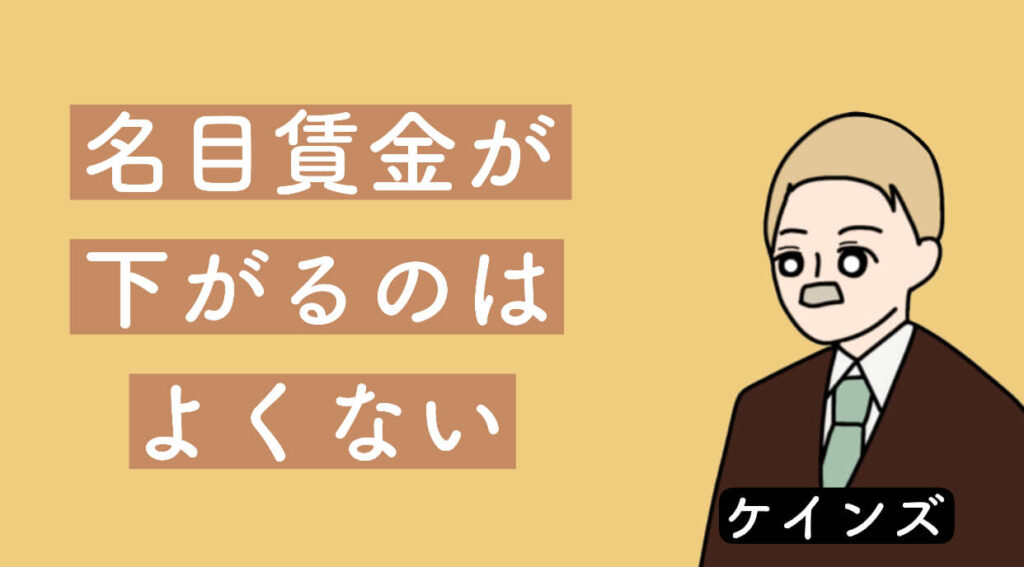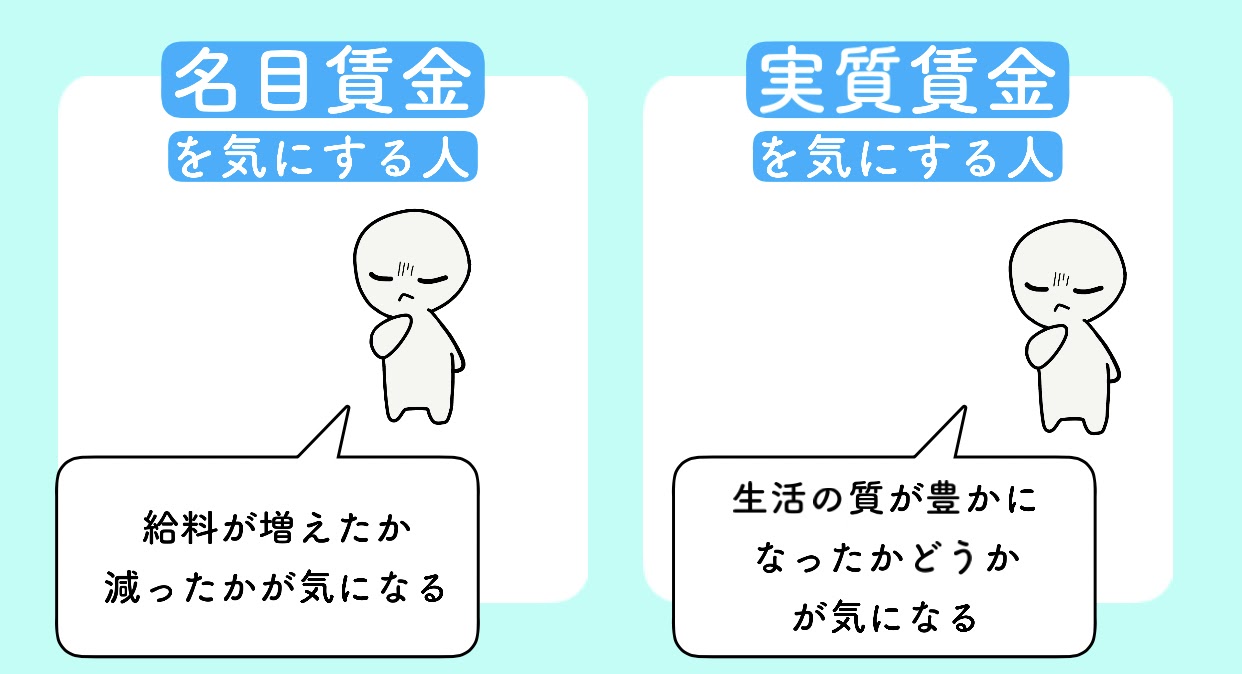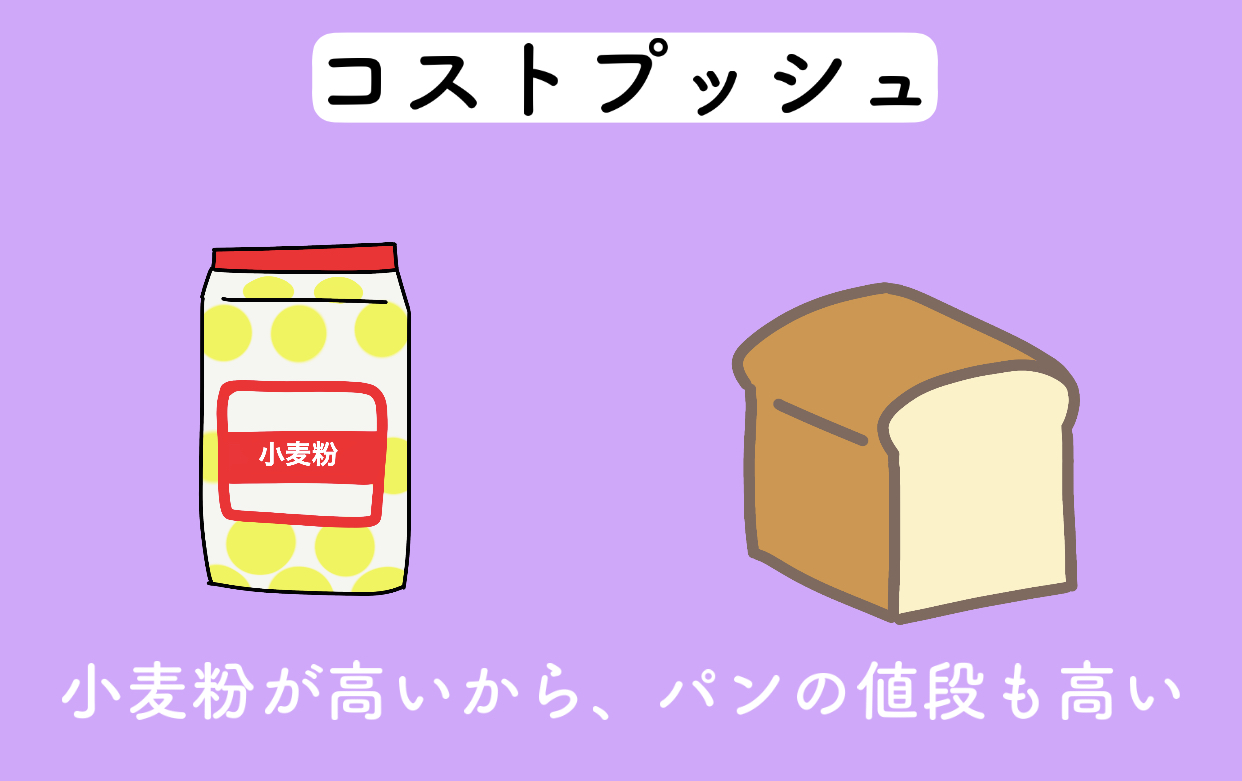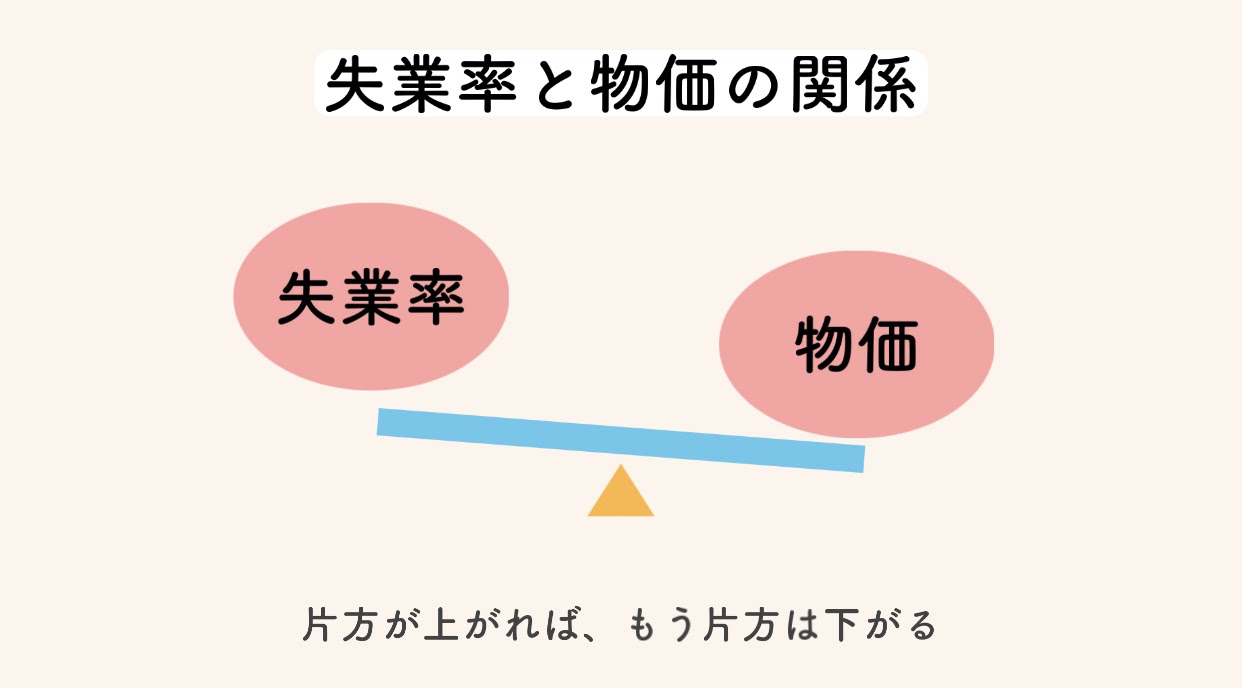ケインズは、『雇用・利子および貨幣の一般理論』という本の中で、名目賃金と、実質賃金の違いについて触れています。
名目と実質は、何が違うのでしょうか?
名目とは、「見かけ上」ということです。
実質とは、「本当の内容」ということです。
名目賃金と実質賃金がどのように違うのか、具体的に見ていきます。
名目賃金とは
まず、名目賃金とは、賃金そのものを指します。
賃金の金額のことが、名目賃金です。
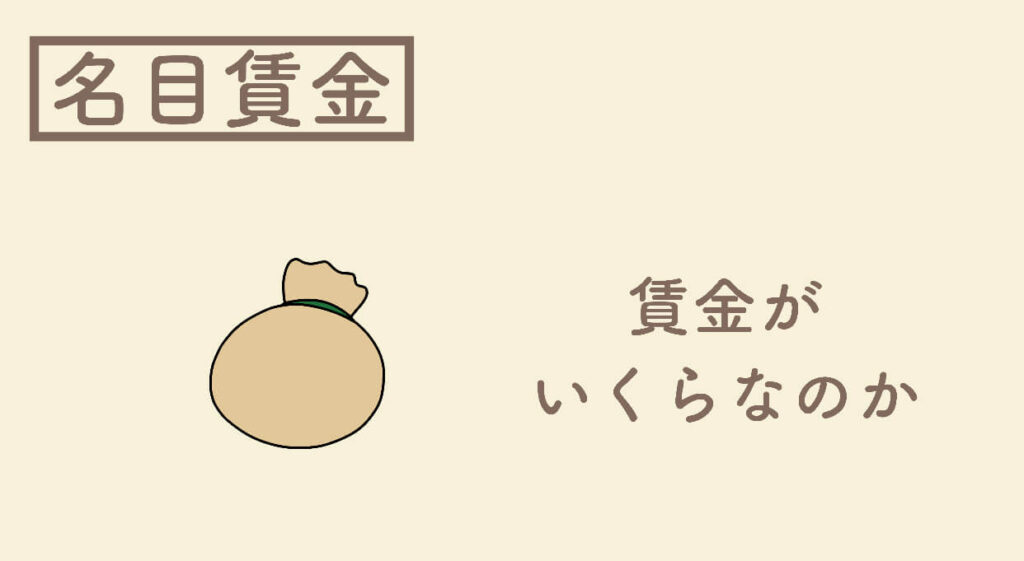
実質賃金とは
一方で、実質賃金とは、物価の変動を考慮した数字です。
実質賃金の数字は、賃金と物価の両方に注目します。
もらった賃金で、どれだけ買い物ができるかを表すのが実質賃金です。
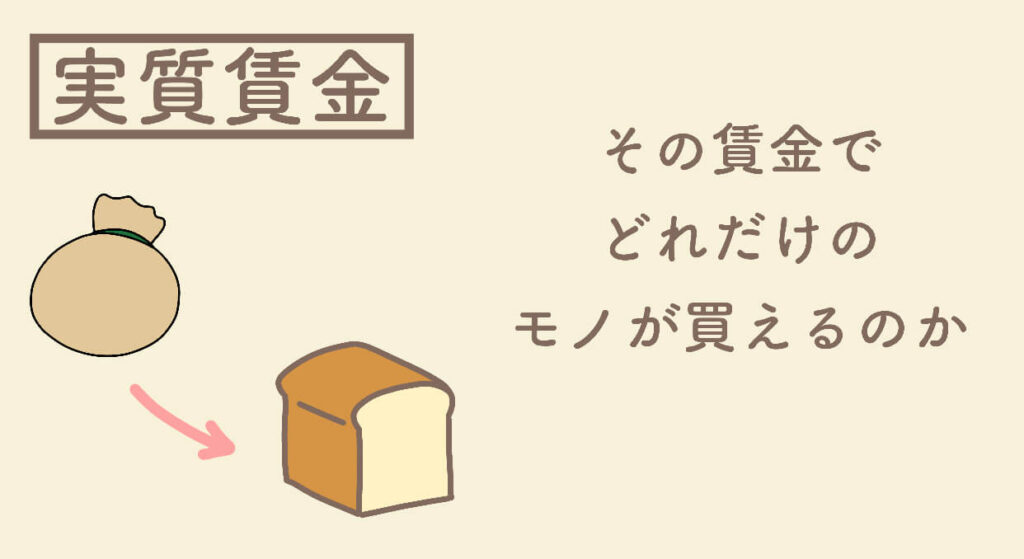
たとえ話
たとえ話をします。
ある日、青年の賃金が100万円になったとします。
そしたら、青年は喜びます。
しかし、パンの値段も100万円になったら、どうでしょうか?
実質的には、豊かになっていません。
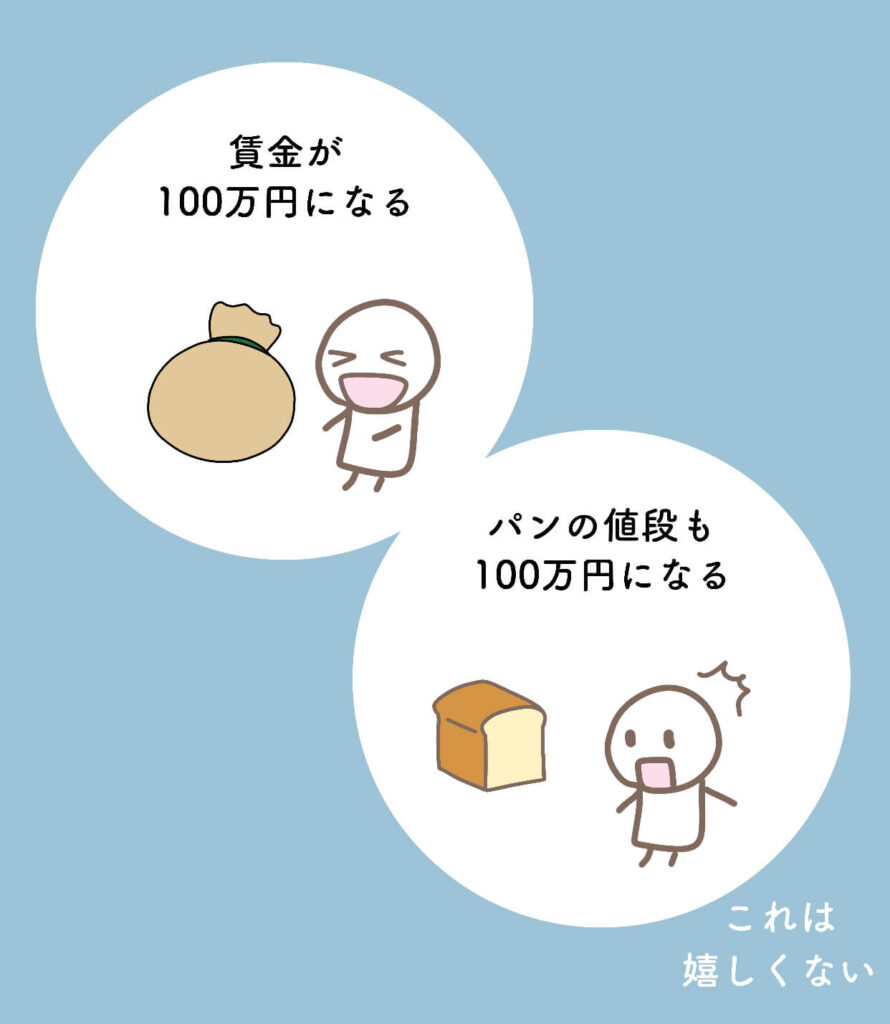
彼の名目の賃金は100万円です。
しかし、名目の賃金が高くなっても、パンの値段も同時に高くなったら、生活は豊かになりません。
実質的には、生活の質は上がっていません。
賃金が上がればいいってわけじゃない
賃金は、上がれば良いってわけではありません。
人は、生活の質を豊かにしたいのです。
賃金が上がっても、パンの値段も上がってしまったら、生活の質は豊かになりません。
だから、賃金が上がれば良いというわけではないのです。
古典派は「大事なのは、実質賃金だ」と考えました。
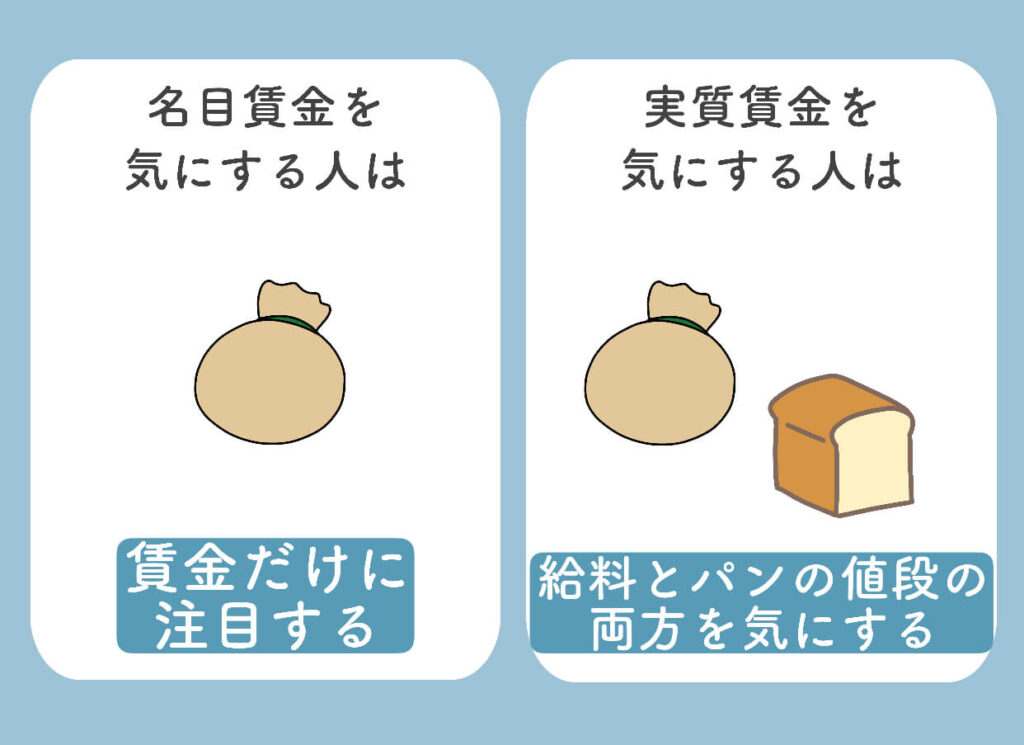
賃金が下がっても、大丈夫
古典派は「賃金が下がっても大丈夫だ」と主張しています。
賃金が下がっても、悲しまなくて大丈夫なときもあります。
それは、パンの値段も下がっている時です。
賃金が下がっても、パンの値段も下がるのであれば、生活の質は変わりません。
特に、世界恐慌のときは、パンの値段は、どんどん下がっていました。
「賃金が下がる=貧乏になる」というわけではないのです。
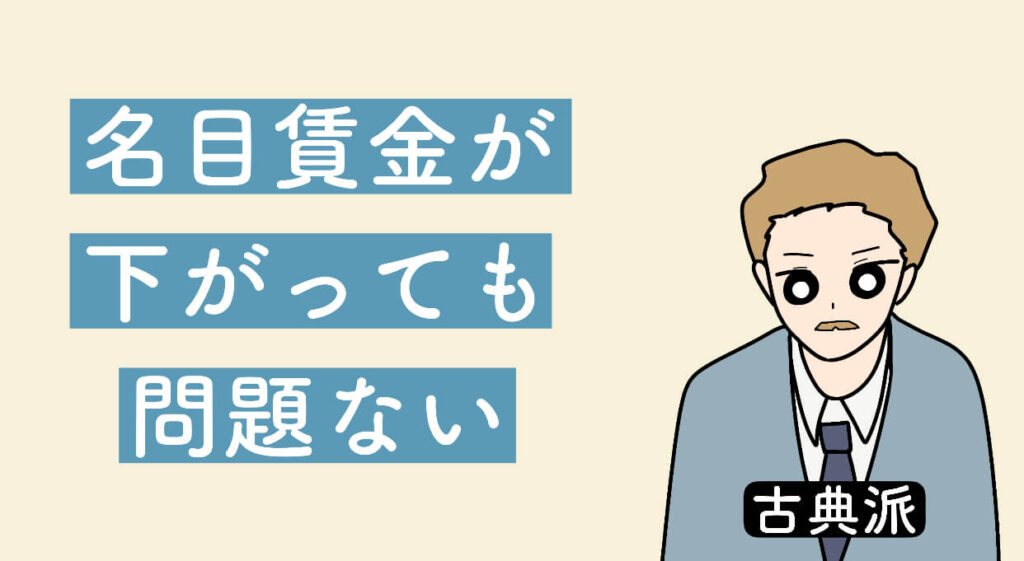
古典派は「自分の賃金だけを見るのではなくて、世の中のモノの値段にも、注目していくべきだ」と言いいました。
生活を豊かにしたいのであれば、実質賃金を見ることが大切なのです。
そのため、古典派は「名目賃金が下がっても問題がない」と考えました。
人は、名目賃金に注目する
しかし、ケインズは、古典派に反論しました。
ケインズは「とはいえ、普通の人は、名目賃金に注目する」と言いました。
名目賃金は分かりやすいからです。
実質賃金は、物価を考慮して計算する必要があります。
普通の人は、そんな計算をしません。
普通の人は、物価の上下にかかわらず、賃金が減ればとりあえず悲しみます。
そして、あわてて節約を始めてしまうものなのです。
だから「名目賃金が下がることは、よくないことだ」とケインズは考えました。